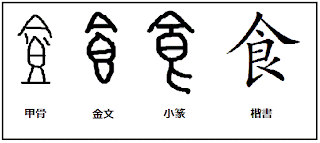人類の活動の基本は「農」にあり!
導入
漢字「農」の由来と変遷:文字に刻まれた農業の歴史
漢字「農」を見れば、昔の人々がどうやって食いつないで来たかが分かる
「農」という漢字の起源:先人たちの生活と文化を紐解く
前書き
人間の数万年のもろもろの活動の中で、結局最も大切なのは「農業」だった。
しかし、特に産業革命以降は、富を生み出すのは工業であり、資本であり、労働力であると信じられ、非常に多くの人々は農業を捨て、工場へ工場へ、と流れ込んだ。その結果、世界津々浦々に工場が林立するまでになっている。
そしてこのことは結果として地球規模での気候変動を引き起こし、人々が食料を確保することさえ困難になっている。
漢字「農」の成立ちを今一度見つめなおし、人類が数万年前に、地上に現れて、非常に長い期間農業を大切にし守り育ててきたにも拘らず、僅かこの2、3百年前までの非常にわずかな期間に、人間が農業ばかりではなく地球を破壊しつくまで至っている。
以上非常に大雑把な見方ではあるが、人類の活動を振り返り、結局最も大切なのは「農業」であることを今一度思いなおすきっかけになればこれ以上の喜びはない。
目次
**********************
漢字「農」の今
漢字「農」の解体新書
| 漢字「農」の楷書で、常用漢字です。 | |
| 農・楷書 |
| 甲骨文は辰は上部は畑の穀物を表す草木の形であり、下部は貝で作った土地用の農具の蜃器から構成される。 金文は田と辰とに従う。甲骨文にはなかった「田」が現れて、井田制による区画を明示した耕作地が描かれている。 小篆になると神饌に専ら使用されたのか「田」の代わりに「囟」が用いられている | |||
| 農・甲骨文字 |
農・金文 |
農・小篆 |
「農」の漢字データ
- 音読み ノウ
- 訓読み たがやす、つとめる
意味
- たがやす(耕)、田畑を耕作する
- 耕作の仕事、畑仕」
- 農業する人
同じ部首を持つ漢字 辰、振、儂、膿、
漢字「農」を持つ熟語 農業、農民、農具、貧農
**********************
漢字「農」成立ちと由来
参考書紹介:「落合淳氏の『漢字の成立ち図解』」
唐漢氏の解釈
甲骨文の「農」の上部は畑の穀物を表す草木の形、下部は「辰」である。青銅碑文の「農」という文字は、草や木の形に「田」という文字を加えて、農地の収穫を表現しています。
漢字「農」の字統の解釈
田と辰とに従う。辰は蜃器。 こうどう 貝で作った耕耨の器で、田と合せて農事をいう。また、林と辰からなる款もある。ト文に艸に従うものがあり、 草菜(草はら)をひらく意を示すものであろう 辰は蜃器で、又(寸)を加えて蓐(草刈る)となる。
漢字「農」の漢字源の解釈
会意文字。甲骨文字は「林+辰」の会意文字で、林を焼き、貝殻で土を柔らかくすることを示す。
「農」に関連する神話、逸話や故事等から農業そのものの歴史や変遷を探る
「農」を取り巻く文化や思想・土地制度に関連するものをいくつか紹介します。
- 神農(しんのう)の伝説
「農」にまつわる最も有名な話は、中国古代の伝説的な帝王「神農」に関するものです。
神農は、農業の神様とされ、人々に農耕技術を伝えたと言われています。また、草木を味見し、その薬効や毒性を確認して医薬を広めたという伝説もあります。「神農百草を嘗む(しんのうひゃくそうをなむ)」という言葉が、そこから生まれました。
神農は、農業を普及させるとともに、人々の生活を豊かにした偉大な存在として語り継がれています。 - 孟子の「五十歩百歩」の教え
中国の思想家孟子が説いた話の中に、農民の努力や苦労に関連する比喩があります。孟子は「農業は国の基盤であり、民を富ませるもの」としながらも、不公正な政策が農業や農民を苦しめることを批判しました。
「五十歩百歩」の故事は、戦争で逃げた兵士が距離の違いを競っているという例え話ですが、孟子は同じように農民を安んじる政策を行わない限り、国は安定しないと説きました。 - 日本の「農業神話」
日本の神話では、天照大神(あまてらすおおみかみ)が穀物を司る神として登場し、豊受大神(とようけのおおかみ)などとともに農業の発展を祝福したとされます。
特に「稲作」は神事と深く結びついており、田植えや収穫の際には祭礼が行われ、神に感謝を捧げる文化がありました。 - 古代の土地制度
中国の井田制(せいでんせい)・・この形から漢字の田ができたといわれています
周代(紀元前11世紀〜256年)に実施されたとされる農業制度で、 農地を「井」の字の形に9区画に分け、中央の1区画を公共用地(税地)として共同で耕作し、残りの8区画を個人に分配して使用するというものです。この制度は、農業を通じて共同体の和を保つための理想的なシステムとされました。 井田制に関する逸話として、「公地公民の理想を掲げた社会でこそ、人々は安心して農業に励むことができる」という教訓が伝えられています。
この制度の歴史的役割
- 共同体の秩序: 農業を共同体全体で支える仕組みを理想とし、封建的な支配体制を基盤にしていました。
- 理念的性格: 実際には広範囲で実施されたかは不明ですが、儒教思想における理想の社会像として語られることが多いです。
この井田制は後に日本の口分田というシステムのモデルケースとなりました。
日本の口分田
時代・背景: 日本の律令制度(7~10世紀頃)の下で、班田収授法に基づき実施された土地分配制度。人口に基づき一定の面積を成人男性や女性に分配。土地の面積は性別や身分で異なりました。 所有権: 土地は公地公民の原則により国家が所有し、農民は耕作権を与えられました。一定期間ごとに再分配されました。 労働力を確保しつつ、税収を安定させるため。稲作を基盤とした律令国家体制の維持が目的。
この制度の歴史的役割
- 中央集権: 国家が土地を一元的に管理することで、中央集権的な律令制を維持しました。
- 人口管理: 戸籍制度と連動しており、農民の労働力や租税を確保する仕組みでした。
漢字「農」の変遷の史観
「農」の長い歴史の中で、漢字も様々な変遷を受けており、文字の変遷をたどることにより、農業そのものの歴史に触れることができます。
甲骨文の「農」の上部は畑の穀物を表す草木の形、下部は石象嵌の線画である「辰」である。
- 甲骨文字
この下部の「辰」の字は、貝の形象説: 最も一般的な説として、二枚貝が殻から足を伸ばしている様子を表しているという説があります。特に、蜃(しん)と呼ばれる大きな二枚貝がモデルになったと考えられています。草を刈る農具「耨(どう)」の形状が「辰」の字の起源になったとする説もあり、逆に太古の昔大きな二枚貝が刈り取りや農具として使われていたという説などあります。
農具を表す「辰」の上部に「田」が使われ、
耕作地であることが明示去れている。
- 金文成立ち(由来)
「農」は、古代中国で農業に関わる概念を表す文字として生まれました。その字形の変遷をたどると、甲骨文には見られず、金文から確認されるようになります。
「農」の字は、もともと「𥥍(農の古形)」として存在し、さらにその元をたどると「辰」と「田」から成ると考えられています。
「辰」:本来、農具(すきやくわ)の形を表す象形文字で、耕作や農業と関係が深い。
「田」:穀物の成長や畑を象徴する部分とされる。
この二つの要素が組み合わさり、「農」は「農作業をする」「耕す」といった意味を持つようになりました。
金文における字形 金文における「農」の字形は、比較的初期のものでは「辰」を中心とし、それに「曲」に類する部分が加わった形でした。金文では筆画が曲線的で、甲骨文のような直線的な字形とは異なり、より整った形状になっています。 金文の中でも時代によって字形に若干の変化があり、次第に後の篆書(小篆)へとつながる形に発展しました。
その後の変遷
金文の「農」は、戦国時代の篆書(小篆)に受け継がれ、秦の時代に李斯らによって統一された公式の字体として整えられました。さらに、隷書・楷書と変化する中で、現在の「農」の形になっていきました。
小篆の上部には文字「囟」文字が使われて、
柔らかな土を耕すという考えが織り込まれた- 小篆
「囟」が「農」の原字に用いられた理由については、明確な定説は確立されていません。しかし、いくつかの説が提唱されており、それらを総合的に考察することで、その理由の一端を理解することができます。
頭頂部の柔らかさと耕作の関連性:
「囟」は頭頂部の柔らかい部分を表し、「農」は土地を耕すことを意味します。
古代の人々は、土地を耕す行為を、頭頂部を柔らかくして新しいものを生み出す行為と重ねて捉えていた可能性があります。
このように、生命の誕生と農作物の成長を結びつけ、「囟」が「農」の原字に用いられたという説が有力です。
まとめ
人類が地上に現れて以降、食料を安定的に確保する営みは営々と続けられてきた。中でも農業はその中心部分を占めてきた。漢字「農」の発展はそれを如実に示している。「農」とたった一字に込められた長い歴史の足跡は見事である。
「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。