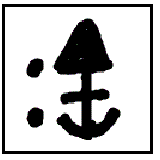人間の欲が社会の中で突き進む姿を漢字から探る
紀元前3000年前に早くもゴールドラッシュが起きていた??
これまでにも世界各地でゴールドラッシュが報告されており、非常に多くの人々が一攫千金を求めて、鵜の目たかの目で金鉱山を探し回っています。
現在では金は貨幣や装飾品に留まらずICチップや集積回路などに広く使われその需要はますます高まっています。
つい先ごろ「中国の 湖南省 地質院は21日、同省平江県で40本以上の金の鉱脈を発見したと発表した」というニュースが世界を駆け巡りました。 その一方で金の採掘選鉱のため水銀が使われていますが、その水銀汚染のためアマゾン流域はずいぶん汚染され、流域の原住民の人々は『水俣病』に侵され苦しんでいると聞きます。
導入
- 人間の社会と金のかかわり 金が人間社会にどう影響を与えてきたか
- 社会の変化と漢字 「きん、かね」を通して見る
- 社会の変化と価値観の係わり 価値観の変化は社会の変化
- 現代社会の歴史的位置づけ いま社会は歴史的にどこに位置するか
- 未来社会がどう動くかの予測
前書き
近年世界的に価値観の変化が起こっているとよく言われます。
誰もがその言葉に納得し、そこである意味思考を停止してしまっている感があります。
価値観が変わるというとき、具体的にどの「価値」が変化しているのかは、社会や時代によって異なります。近年でよく言われる価値観の変化には、例えば以下のようなものがあります。
- 働き方に関する価値観
「終身雇用」→「転職やフリーランスの自由な働き方」
「仕事中心の人生」→「ワークライフバランス重視」
「年功序列」→「成果主義・実力主義」 - 家族・結婚に関する価値観
「結婚・出産が当たり前」→「結婚しない・子どもを持たない選択も尊重」
「専業主婦が理想」→「共働き・家事のシェアが当たり前」
「家族の形は一つ」→「多様な家族の形が認められる(同性婚、事実婚など)」 - お金・消費に関する価値観
「高級ブランド志向」→「ミニマリズム・サステナブル消費」
「所有することが重要」→「シェアリングエコノミー(サブスク、カーシェアなど)」
「貯蓄が大事」→「経験や自己投資にお金を使う」 - 性別・多様性に関する価値観
「男らしさ・女らしさの固定観念」→「ジェンダーレスな生き方」
「マイノリティは隠すもの」→「多様性を尊重し、オープンに」 - 環境・社会意識に関する
「個人主義」→「共助・コミュニティ意識の高まり」
ここではその価値観を「金」(かね、きん)に絞った上で、ここは漢字のページですから、漢字の「金」を通して見つめなおしたいと思います。しばらくお付き合いください。
目次
**********************
この記事は以前にアップしたものをリバイスしたものです。
漢字「金」の今
| 漢字「金」の楷書で、常用漢字です。 上部は「今」で、語義は、貴金属の金、貨幣の「かね」を表します。 「金」という文字はやはり不思議な力を持つようで、片や多くの人々のあこがれであるし、方は底知れぬ力で、人々を支配するものです。 しかしそういった力は「金」に最初からあったわけではなく、資本主義の世の中で、金本位体制が長く続き、金が資本として、世界を君臨してきたからでしょう。 そして漸く資本主義の終焉が叫ばれてきてはいますが、新しい世界は目の前に姿を現しません。共に新しい世界を探ろうではありませんか | |
| 金・楷書 |
漢字「金」の解体新書
| 金・甲骨文字 上部は銅液の流出を表し、下部は「火」を表し、全体として溶錬を示す |
金・金文 下部は一つの書き方では土から出来ている。即ち土(鉱石のことを示しているが)の中から冶煉で出来たことを示している。 |
金・小篆 金文を受け継ぎ、「今」と「土」と二つの点から出来た会意文字 |
「金」の漢字データ
- 音読み キン・コン
- 訓読み かね・こがね
意味
- 材質
- 貨幣を表す
- 反射光を持つ黄色
同じ部首を持つ漢字 銅、鉄、
漢字「金」を持つ熟語 金色、金環、金字
漢字「金」成立ちと由来
参考書紹介:「落合淳氏の『漢字の成立ち図解』」
金は古代にあっては銅のことを称していた。その後金属類の総称となり、最後にはやっと専ら黄金の名前となった。
甲骨文字の「金」の字は上下部の繋がった構造となっている。下辺は「火」であり、火で熔煉を表した。「金」の字の本義は銅であり、青銅の銘文の中で「吉金、赤金、美金」などから分かる。この中の「金」は全て銅を指している。
会意兼形声。今は「抑えた蓋+一」から成る会意文字で、何かを含んで抑えた形を表す。「金」は「点々のしるし+土+音符今」で土の中に点々と閉じこもって含まれた砂金を表す。
象形文字:銅塊等鋳込んだ形。説文に「五色の金なり」とし、金の土中にある形に今声を加えた形とするが、字は今声に従うものではない。金文の字形は全形の左右に楕円形の小塊二を添えている。
漢字「金」の変遷と社会
「金」以前の貨幣
人間の社会が形成されるまでの歴史を振り返る
旧石器時代(Paleolithic Age)時代区分:約250万年前~1万年前
今から約250万年前類人猿としてではなく人類としてこの地球上に現れて一万年前までの長い長い期間、打製石器(石を打ち砕いて作る石器)を用いて、狩猟・採集が中心(遊牧や農耕はまだない)にして、洞窟や簡易な小屋を利用しながら家族などの極めて小さなまとまりで狩猟採集を主体とした移動生活を送っていました。
このころの世界はある意味平和で、人々は自然に対する闘いは熾烈を極めていたかもしれませんが、少なくとも、人間同士の戦いや争い、戦争もそれほど多くなかったのではないかと考えられます。
新石器時代(Neolithic Age)時代区分:約1万年前~紀元前3000年頃(地域によって異なる)
- 石器の進化:磨製石器(石を研磨して作る石器)を使用
- 土器の使用:食料の保存や調理のために土器が作られる
- 農耕・牧畜の開始:小麦・大麦の栽培、家畜の飼育(ヤギ、牛、羊など)
農耕・牧畜が始まったことが今後のあらゆる面での大変革となりました。 - 農耕が発展し生活が安定したことにより、余剰が産出され、富の集積がはじまり、力の強いもの、大家族が独占的に富を集積するようになりました。
このことは奴婢や奴隷を持ちその労働を収奪することで、いっそうの富の集積が可能となり、奴婢や奴隷の獲得を求めて、争いや侵略や略奪が起こるようになりました。 - 定住生活:農耕による食糧供給の安定により村落が形成される
- 社会の変化:階層社会の形成、交易の発展
農耕の始まりはそれまで続いてきた母系制社会の崩壊を意味し、妊娠や子育てに多くの労力をとられる女性に変わり、腕力が強い自由度の高い男性が次第に力を得るようになり、社会は父系制社会へと変貌することになります。それはその後も続き秦の始皇帝の時代で完成することとなります。
旧石器時代は「狩猟採集を主体とした移動生活」、新石器時代は「農耕牧畜を伴う定住生活」
この変化は氏族制度の始まりとほぼ一致します。- 始まり:紀元前8000年頃(新石器時代の初期、農耕開始とともに)
- 発展:紀元前5000年頃〜3000年頃(部族の形成と階層化)
- 完成:紀元前3000年頃〜1000年頃(氏族社会が貴族支配の国家へ移行)
つまり、氏族社会は新石器時代に始まり、青銅器時代〜鉄器時代にかけて階層化が進み、最終的には王権を中心とした国家形成へと移行 していきました。 この男性有利の社会は3000年後の今日まで依然として続き、近年ようやく変化が見え始めているといっていいでしょう。
ここで改めて、「社会のあり方」に基づいて時代区分を整理すると、以下になります。
狩猟採集社会(平等・移動生活)旧石器時代、新石器時代 農耕牧畜社会(定住化・階層化の始まり)氏族社会、青銅器、鉄器時代
国家形成社会(都市・階級社会・文字の発明):(紀元前3000年ごろ~中世
封建社会(領主制・宗教支配・商業発展):(中世~近世、5世紀~18世紀)
産業社会(資本主義・民主主義・機械化):(18世紀~20世紀半ば)
情報社会(IT・グローバル化・知識経済):(20世紀半ば~現在)
ポスト情報社会(AI・自動化・未来の可能性):(未来予測)(21世紀後半以降、予測段階)
「金」貨幣及び金の価値の変遷
以上のような歴史的変遷の中で、氏族社会が生まれ貧富の差が生じ、階層が生まれ富が蓄積されるようになっても、金や貨幣が実際に流通の中で用いられるようになるのは紀元前1000年あたりまで待たなければなりませんでした。
 |
| 貝による貨幣(南海諸島にて購入) |
交易がおこなわれようになった最初のころは貨幣は貝殻でできたものでした。その貝もも二枚貝で子安貝のような種類が多く使われたといいます。これは貝は手に入り易かったからでした。
したがってこのころできた古代の漢字には「貝」が使われており、私達も現在「財、貨」などの多くの漢字にそれを見ることができます。
さらに紀元前1500年前の殷や周の時代には漢字の「金」という字は既に使われていましたが、このころの「金」という文字は実際にはGoldの金ではなく、銅の合金である黄銅を指していたということで、今の「金」が実際に使われるようになったのは、もうしばらく後のことになります。
 |
| 地図の中にある緑の旗印が古代都市「ウル」 |
人類が最初に金を採掘したのはメソポタミアの北部や東部の山岳地帯にある金鉱脈で古代から金が採掘されていたのではないかと言われています。
人類と金の係わりは古くメソポタニア文明の栄えた今から約6000年ほど前、シュメール人が現代のイラク南部に位置する古代都市「アッカド」や「ウル」の近郊で金の採掘をしていたという記録が残されています。
中国における金の採掘は、少なくとも商王朝(紀元前1600年頃 - 紀元前1046年頃)の時代には始まっていたと考えられています。これらの金は王侯貴族の装飾品として用いられており、貨幣として用いられるようになるのはずいぶん時代が下ってからになります。
経済活動を支える重要な役割を果たすようになるのは、春秋戦国時代(紀元前771年 - 紀元前256年)に入ってからになり、この時代には、金が貨幣としても流通し始め、各地で金鉱山の開発が活発化しました。中国で金の採掘がはじまったのは紀元前1600年程の商王朝に遡るといわれています。中国における主要な金産地は、山東省、河南省、江西省、雲南省などです。
価値観の変遷と社会の向かう先
金に対する価値観は、歴史的に大きく変化してきました。
- 古代
金は、その希少性と美しさから、古代文明においてすでに特別な価値を持っていました。
装飾品: 金は、その美しい輝きから、装飾品として珍重されました。
貨幣: 金は、その高い価値と安定性から、貨幣としても使われました。
権力の象徴: 金は、その希少性から、権力や富の象徴としても使われました。 - 中世 中世ヨーロッパでは、金はキリスト教教会や王侯貴族の財産として重要視されました。
中世は基本的に封建制を基盤とする仕組みで、経済は土地・荘園に基づく農業でした。
教会の装飾: 金は、教会の装飾や祭具として使われました。
王侯貴族の財産: 金は、王侯貴族の財産として蓄えられました。
錬金術: 中世ヨーロッパでは、金を生成しようとする錬金術が盛んに行われました。 - 近世 大航海時代以降、ヨーロッパ諸国は、金や銀を求めて世界各地に進出しました。
マルコポーロの「東方見聞録」が書かれ、日本が黄金の国として世界に登場しました。
世界は全体主義国家に大きく舵を切り、それまで行われていた「土地の囲い込み運動」は影を潜め、逆に囲いを取っ払い統合し新しい世界の構築が模索されるようになりました。
ヨーロッパでは宗教改革が起こったのも、宗教の壁を取り除きより多くの利潤を求める人間のあくなき欲望の表れともいえるでしょう。
アメリカ大陸が発見され、アフリカ大陸が植民地として蚕食され、悲惨な結果を招きました。
重商主義: 獣金主義金や銀の蓄積は、国家の富の象徴と考えられました。
植民地支配: 金や銀を求めて、多くの国が植民地支配を行いました。 - 現代現代社会では、金は投資対象としての価値が注目されています。
中世と近世で人間は地理的に拡大しつくし、拡大の余地がなくなってしまいました。
次に資本が目に付けたのは国境をなくし、手さらなる利益の増殖を図ることでした。
結果として、グローバリズムが叫ばれ、企業が国境の壁(規制)を取り払ったり、緩和させたりしました。
人間の欲望はそれに飽き足らず、リアルの世界とバーチャルの世界の壁を取り払い更なる増殖を図っています。
ドルの金本位体制が崩壊した今日、金は基軸材として機能していますが、今や仮想通貨がリアルの通貨の流通量を上回っている現実があります
仮想通貨を流通させるプラットフォームのヘゲモニーをどこが握るかの争いになっています。
インフレヘッジ: 金は、インフレに対するヘッジとして、投資家によって買われます。
安全資産: 金は、世界経済の不安定化時に、安全資産として買われることがあります。
宝飾品: 金は、宝飾品としても人気があります。
まとめ
以上のように漢字「金」という一文字についても、その変化の背景には長い歴史的、社会的変化、変遷の過程があり、漢字の持つ奥深さがよく理解できると思います。
金に対する価値観は、時代とともに変化してきました。古代から中世にかけては、装飾品や貨幣、権力の象徴として重要視され、近世には国家の富の象徴として注目されました。現代では、金に対する価値観の変化に留まらず、バーチャルな世界に対する骨肉の争いも問われている中で、アメリカではトランプ政権が「アメリカ第一主義」を唱えて、登場しましたが、「アメリカ唯一主義」ではないかと疑わせる主張で、世界に混乱を巻き起こしています。
価値観の変化は社会の変動であり、私たちは今後世界はどちらに向かうのか目先の事柄に囚われることなく、しっかり監視しなければなりません。自らの生き残りをかけて!
| 「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。
|