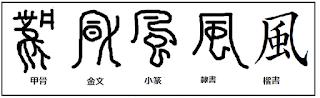漢字「猪」の起源と由来は猪豚ではない
今まで、いのししというとともすれば干支の「亥」について触れることが多かったが、ここでは原点に戻り、干支のいのしし「亥」から少し離れて、「猪」という漢字そのものと動物の関係ついて考察してみよう。イノシシは長い間に飼い馴らされて、猪豚になり、豚になった。この間数千年の時が流れる。

「猪」の字の成り立ち」
「猪」はるか昔の時期人々は、豕と称していた。つまり「猪」という漢字が出来る前には、所謂「猪」を「豕」と書いていた。 現代でも猪の「繁体字」は「豬」という字が用いられるが、「説文解字」にも「豬」が収められている。しかし猪という漢字は、秦代以前にも既にあったということである。
甲骨文字の豕は、象形文字であり、口が長く、足が短い。腹は丸々肥えて、尻尾は下に垂れ下がる。横から眺めてみると、将に一頭の太った猪のそっくりそのままのデッサンを書いている。
「豕」は「猪」にどのように代わって行ったか
はるか以前の先民から見ると「豕」は六畜(牛、羊、豕、馬、犬、鶏)の一つである。人類の最も早い馴化養育した家畜であり、猪はきわめて不安定な狩猟を補充する生活の道を講ずる方式を補充するものであったと見ていい。飼育されるようになった豕は、自然に食糧の備蓄として当てられるようになった。
即ち、「豕」は非常に長い年月を経て、人間に馴化し、人間の食糧補給として、人間と共に生きてきた。そして馴化した猪は、まるで人間について回る付帯動物のように認識されてきたのではないか。「豬」の旁の「者」は元々漆器の器物上の大きな漆塗りで著わしたものを指すことから、人間に付帯するものとして、「豕」に「者」を付け加えるようになったのではないかというのが、唐漢氏の説のようである。
「豕」にかかわる古事来歴
遼東の豕(いのこ)
時は後漢の光武帝の治世のころ、今の北京・天津の辺りの彭寵という太守の不穏な動きを大将軍朱浮が戒めた中で、使われた言葉で、「他から見れば異とするに足らない功を誇る」「他から見れば当たり前のことを自ら奇異だと誇る」という意味た。これは朱浮が、「遼東の辺りで白頭の豚の子が生まれたので、これは変わった豚だと王に献上しようとした者が江東まで行くとその地の豚は皆白かったので、恥じて帰った」という逸話から引いて戒めたという話がある。
このような話は、いつの世でも塵芥のごとく散らばっており、どこかの首相や大統領にもこの手の話は尽きないようである。
| 「漢字の起源と成り立ち 『甲骨文字の秘密』」のホームページに戻ります。
|