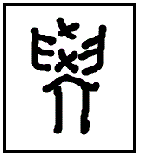漢字「人」は、人間のどの様な状態から生まれたのか? 少しひざを曲げた側身を表したもの
導入
前書き
人という字は、お互いに助け合うから二本の線が寄りかかったような形をしているのだという説がある。これは文字学者から言えばとんでもない誤解だということである。
この「人」という字は象形文字であって、足で立ち上がった様子を側面から眺めたものだということが定説のようである。
ここでは、なぜ側面からの立像なのかの理由も追及してみたい。
目次
**********************
漢字「人」の今
漢字「人」の解体新書
| 漢字「人」の楷書で、常用漢字です。 | |
| 人・楷書 |
| 人・甲骨文字:前かがみで、腰が少し引け、膝をを曲げ、次の行動に移りやすい姿勢をとっている |
人・金文 真ん中から左斜め下に突き出した線が足であるとは言い難いのだが |
人・小篆 図形を文字化する際の一様性が出ているのか |
**********************
「人」の漢字データ
- 音読み じん・にん
- 訓読み ひと
意味
- ひと
- 数量詞
- 人種を表す集合名刺
同じ部首を持つ漢字 作、儀、供、伴、侶、備
漢字「人」を持つ熟語 人類、人間、人類、殺人
**********************
漢字「人」成立ちと由来
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)唐漢氏の解釈
「人」之は典型的な象形文字である。図に示すように典型的な象形文字です。 図に示されているように、「人」という字のイメージは、横向きの人の立像で、甲骨、金文、小篆および楷書体で、全て簡潔で明快な線状の組み合わせです。「説文」はこのことを述べています。 これはまさに人体の突出した四肢と明確に使い分けられた手と足を示しており、人の特質を示しています。また側立の形を用いて、人と動物の典型的な特徴を示してる。
「人」の字は単純で、振りかけるのは1つだけですが、古代人の物事の観察の綿密な精度と精度を反映しており、古代人が自分自身を理解する能力を示しています。人と他の動物の主な違いは、手足、人と動物の違いは直立して歩くことであり、人間は両手を解放して道具を使用することが可能になった。
漢字「人」の字統P479の解釈
象形字 人の側身の形。説文に「天地の性、もっとも貴きものなりとする。」卜文、金文ははみな側身形、匈、包、身などみなその形に従う。夷の卜文、金文の字形もこれに近く、いくらか膝を屈する形に作る。
漢字「人」の漢字源の解釈
象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や 隣人仲間を意味した。
孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大広く隣人愛の心を仁(ヒューマニズム)と名づけた。
【単語家族 二(二つくっついて並ぶ) 爾(そばにくっついている相手、なんじ)・尼(相並び親しむ人)・仁と同系。
漢字「人」の変遷の史観
文字学上の解釈
| 第1図 「人」・甲骨文字 | 第2図 人偏・甲骨文字 |
「人」の甲骨文字は、字統には、左の第1図のごとく、人の側身の形。説文に「天地の性、もっとも貴きものなりとする。」卜文、金文はみな側身形、匈、包、身などみなその形に従うとある。
以下「人」という漢字はこれが基本形となっている。さらに人偏の甲骨文字は、左の第2図の通りである。人偏は、まずは対象を明示し、部首や旁と共に、漢字における人間の属性を示す。
さらに部首の中に入って、文字の在り方を示す。(例:囚、閃)
まとめ
古代人の観察の細かさ、表現の豊かさには本当に感心する。漢字「人」は基本的な漢字として、実に多くの概念を派生しながら生き続けてきた。漢字の「人」の旁や偏を通して漢字が如何に構成されているかを見たが、非常に構造的に、機能的に構成されており、実に論理的な思考がなされているか感嘆する。これが文化だ!
これらは分化する前の中華民族の優秀さをいまさらながら誇示しているように思う。
| 「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。
|