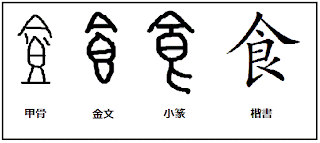 |
| 「食」の原義は足の高い食器(「豆」と書いた)に 盛り付けられた食物の意味 |
小篆の食の字は下部は既に食器の形らしからぬようになっているが、但し形上は却って美観になっている。
楷書は即ち単純な文字の符号に変化し、甲骨文字の「食」の字の下部の「豆」と書くのは、原本は古人が、稗粟、稲、高粱等の主食を盛り付けた食器である。「食」は名詞で、専ら主食を指し、後に食物一般を指すようになった。「食」の字は殷商の卜辞の中では一つは「食べる」意味で、二つ目は食事の時間を表した。卜辞の中の「大食」の様なことは、即ち午前8,9時の食事の時間を言う。また朝食(大食、意味は腹いっぱい食べる);「小食」は午後4、5時の時間で、又「饗」(「小食」、意味は晩方未だ祭祀後の飲食に関連している。)この種の飲食の習慣は大采、「小采」という類の労働の習慣に適応し、即ち日の出から8,9時の労働は大采となり、十時から午後3,4時の労働は「小采」となった。
食の本義は己の好むだけ盛り付け男の食物を残しておくことである。(少し回りくどいが・・。)また男たちが帰って来てから一緒に食べることを表す。この故に、一般的な意味の食物に拡張された。また名詞から動詞の「食べる」という意味も引き出された。
この事から当時の生活様式や労働様式が垣間見える。
| 「漢字の起源と由来ホームページ」に戻ります。
|
