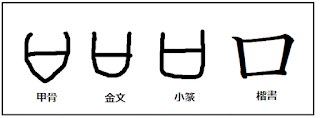漢字「疑・嫌」はいずれも「疑い」示すことは疑いようがない。この二つの言葉の真の違いが今明らかになる。
漢字・疑の成り立ちと由来:人は疑う動物である。3500年前から今に至るまでDNAに受け継がれている。今や疑惑の時代言い換えればフェイクの時代!
漢字・疑の成り立ちは自分はどうすべきか、凝然と立ち尽くす様をしめす。この姿は甲骨文字から一貫して今も全く変わらない。今でも人は進むべきか留まるべきか迷い続けている漢字を見れば歴史がわかる。人の世の移り変わりが分かる。この漢字「疑」も甲骨文字では、人が単に立ち止まって凝然としている様をあらわしていたものが、金文になると道が加わり、道路が整備されたことがわかり、さらに「牛」まで付け加えられ、失われた牛を探すと言う有様まで表すことから、世の中で農業が盛んになり牛を農耕に使うようになったことが推察されます。
このように一つの漢字だけからでも人るの歴史物語が出来てしまいます。
「疑」の漢字データ
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)
漢字・疑の成り立ちと由来:人は疑う動物である。3500年前から今に至るまでDNAに受け継がれている。今や疑惑の時代言い換えればフェイクの時代!
漢字・疑の成り立ちは自分はどうすべきか、凝然と立ち尽くす様をしめす。この姿は甲骨文字から一貫して今も全く変わらない。今でも人は進むべきか留まるべきか迷い続けている漢字を見れば歴史がわかる。人の世の移り変わりが分かる。この漢字「疑」も甲骨文字では、人が単に立ち止まって凝然としている様をあらわしていたものが、金文になると道が加わり、道路が整備されたことがわかり、さらに「牛」まで付け加えられ、失われた牛を探すと言う有様まで表すことから、世の中で農業が盛んになり牛を農耕に使うようになったことが推察されます。
このように一つの漢字だけからでも人るの歴史物語が出来てしまいます。
| 漢字「疑」の楷書で、常用漢字です。 甲骨文も、金文も一様に人が立ち止まり凝然として行く手を決めかねている様が生き生きと描かれている。まさに百聞は一見に如かずである | |
| 疑・楷書 |
| 疑・甲骨文字 人が後ろを向いて凝然と立ち杖を立てて進退を決めかねている様子 第2款・・道路を表す「符号」を追加して、意味をより明確にしている |
疑・金文 甲骨文を継承し、左辺には牛の記号が付け加えられ、右辺下部に「足」を追加して、歩いていくことを意味しています |
疑・小篆 金文では牛を探したものが、小篆では子供を探すさまが付け加えられている。人々の視点が農業から人間社会に変化したと考えられる |
「疑」の漢字データ
漢字の読み
意味
同じ部首を持つ漢字 凝、擬、嶷
漢字「疑」を持つ熟語 懐疑、危疑、疑義、疑獄、疑心、疑惑
- 音読み ギ
- 訓読み うたが(う)
意味
- うたがう (動詞) 本当かどうかあやしく思う
迷う、ためらう
怖がる、不安になる - うたがわしい(形容詞) 本当かどうかあやしい
- うたがい(名詞)
同じ部首を持つ漢字 凝、擬、嶷
漢字「疑」を持つ熟語 懐疑、危疑、疑義、疑獄、疑心、疑惑
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)
唐漢氏の解釈
「疑」の本意は、惑わされることを指し、確定する方法がないことを言う。甲骨文の「疑」という言葉は、杖をもって出た人が左右うろうろと、道に迷い、どこに行けばいいのかわからないことを示しています。甲骨の別の書き方では、道路を表す「符号」を追加して、意味をより明確にしています。
金文は甲骨を継承していますが、下部に「足」を追加して、歩いていくことを意味しています。加えられた「牛」は失われた牛を探すことを意味します。これにより、「疑い」という言葉の構成がより鮮明になり、金文の時期に農耕が重要な地位を占めていたことを反映してます。
小篆は変化を遂げていく過程で、人が振り返った人の頭の形を「匕」とし、人の形の「大」は「矢」に変化し右の牛の形も変化して「子」になっています。次第に今日の楷書の「疑い」になります。
「疑」とは
「疑」の本意は、惑わされることを指し、確定する方法がないことを言う。甲骨文の「疑」という言葉は、杖をもって出た人が左右うろうろと、道に迷い、どこに行けばいいのかわからないことを示しています。甲骨の別の書き方では、道路を表す「符号」を追加して、意味をより明確にしています。
金文は甲骨を継承していますが、下部に「足」を追加して、歩いていくことを意味しています。加えられた「牛」は失われた牛を探すことを意味します。これにより、「疑い」という言葉の構成がより鮮明になり、金文の時期に農耕が重要な地位を占めていたことを反映してます。
小篆は変化を遂げていく過程で、人が振り返った人の頭の形を「匕」とし、人の形の「大」は「矢」に変化し右の牛の形も変化して「子」になっています。次第に今日の楷書の「疑い」になります。
「疑」とは
漢字「擬」の漢字源の解釈
子供に心が引かれ、親が足を止め、どうしようかと思案する様
「疑」と同様の意味を持つものに、「嫌」(うたがう)がある。こちらはこうではないかと気を回しておもう、悪い方へと連想する。今日われわれは疑うというと、こちらの意味に使うことが多いように思う。
子供に心が引かれ、親が足を止め、どうしようかと思案する様
「疑」と同様の意味を持つものに、「嫌」(うたがう)がある。こちらはこうではないかと気を回しておもう、悪い方へと連想する。今日われわれは疑うというと、こちらの意味に使うことが多いように思う。
漢字「疑」の字統の解釈
象形文字 初文は「ヒ+矢」(ギ)人が後ろを向いて凝然と立ち杖を立てて進退を決めかねている様子で、心の疑惑している様を示す。後にまた足の形を加えて今の字形となったが、初形はかなり失われている。
説文の解説は既に字形の初形を失っている篆書の字形によっていうもので、そこから字形を解くことはできない。
象形文字 初文は「ヒ+矢」(ギ)人が後ろを向いて凝然と立ち杖を立てて進退を決めかねている様子で、心の疑惑している様を示す。後にまた足の形を加えて今の字形となったが、初形はかなり失われている。
説文の解説は既に字形の初形を失っている篆書の字形によっていうもので、そこから字形を解くことはできない。
まとめ
単なる思い付きであるが、漢字の生成時期はいくつかのステージに分かれると思っている。即ち、文字の創成期、文字の広範囲に使われる時代、卜文などで、権力に取り込まれる時代そして、完成期。思い付きが、確証になることを望む。漢字「疑」は、迷うと考えた方が原義に近い。いわゆる人を「うたがう」という意味では、「嫌」に近いようである。
単なる思い付きであるが、漢字の生成時期はいくつかのステージに分かれると思っている。即ち、文字の創成期、文字の広範囲に使われる時代、卜文などで、権力に取り込まれる時代そして、完成期。思い付きが、確証になることを望む。漢字「疑」は、迷うと考えた方が原義に近い。いわゆる人を「うたがう」という意味では、「嫌」に近いようである。
| 「漢字の起源と成り立ち 『甲骨文字の秘密』」のホームページに戻ります。
|