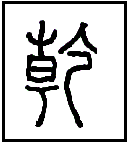漢字「去」の成立ちと由来:「去」は神の神前で審判を仰ぐ時に用いた厳粛なツールに由来した
今では法はある種のご都合主義的に使われ、国法の最高の憲法ですら、ないがしろにされている雰囲気がある。
しかし、太古の昔は「法」の原字ともいえる「去」は、大変な重みづけをもっていたようである。「去」は太古の昔から存在した字であるが、その昔はある種アミニズムの権威付けのツールにも使われたのではと思われる。神の前に審判を仰ぐ器であったと考えられ、審判に敗れれば、器と敗れた人とともに水に流すことを法といった。非常に厳しい戒律であったようだ。これらのことは、「法」は決して疎かにするべきものではないことを、我々に教えている。
導入
前書き
目次
**********************
漢字「去」の今
漢字「去」の解体新書
| 漢字「去」の楷書で、常用漢字である。 | |
| 去・楷書 |
| 去・甲骨文字 |
去・金文 |
去・小篆 |
「去」の漢字データ
- 音読み キョ、コ
- 訓読み さる
意味
- ゆく、去る
- しりぞく
- やめる
- 過ぎる
同じ部首を持つ漢字 去、蓋、法、怯、劫
漢字「去」を持つ熟語 去、過去、去就、死去
**********************
漢字「去」成立ちと由来
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)唐漢氏の解釈
大と口とからなる会意語である。「大」は人の正面の形で、「口」は町や村を示していること、またはくぼんだ形の「坎」を意味することもある。 したがって、「去」という言葉は、人が穴を跨いで、村や町を通り抜けたりするイメージから取られ、立ち去る、または立ち去ることを意味する。 「残る、去る、死ぬ、辞任する」などの慣用句や「どこへ行く、去っていく」など。
漢字「去」の字統(P180)の解釈
会意 大と凵(カン)とに従う。大は人凵は蓋を外した器。神判で敗れたものは、神判に当って盟誓した自 己詛盟に偽があるわけであるから、その祝禱の器で あるの蓋を外して凵とし、その人とともにこれを棄去する。
わが国の大祓詞にいう汚穢を水に流すことと、祓うという 観念において、共通する罪悪観である。廃棄の意より、場所的にその場を去る意となり、時間的には過去に隔たる意となる。 故郷を棄てることを、大去という。
漢字「去」の漢字源(P224)の解釈
象形:蓋つきのくぼんだ容器を描いたもので、窪んだ籠の原字。くぼむ・ひっこむの意を含み、却と最も近い。転じて現場から退却する。姿を隠すの意となる。
漢字「去」の変遷の史観
文字学上の解釈
漢字「去」には、甲骨文、金文にもそれなりの款が存在している。
去は神の前で、審判を仰ぎ、審判に敗れれば去る。その時水に流すのが法、審判に用いた器と共に捨てるのが灋である。
いずれにせよ、審判を受けることは並大抵のことではない。
まとめ
これに関しては、(白川静「字統]P180)の説明が最も理にかなっているように思う。曰く、大と凵(カン)とに従う。大は人凵は蓋を外した器。神判で敗れたものは、神判に当って盟誓した自己詛盟に偽があるわけであるから、その祝禱の器であるの蓋を外して凵とし、その人とともにこれを棄去する。これを水に流す字は法、神判に用いた解廌をともに棄てるときは灋となる。灋は金文において廃棄の意に用いる字である。| 「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。
|