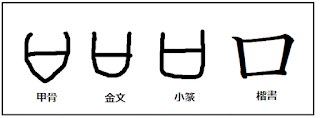漢字「口」は、祝禱を入れるサイなのか、或いは食べたり、話したりする普通の口なのか
「口」という文字は、象形文字でその形状は非常に単純で、容器以外考えようがない。形状から見ると、祝禱や固形物を入れるよりも液体を入れる容器のように思える。
しかし、わが国の漢字学の権威の白川静氏は、これをサイと呼び、祝禱を入れる器と解釈した。
氏は「従来の説文学において、口耳の口に従うと解するために字形の解釈を誤るものは極めて多く、古・召・名・各・吾などに含まれる「口」は全てサイと解釈すべきものを誤解したものだ」と喝破されている。しかし、私には、この単純な「口」という文字が、逆に、ほとんどがサイと呼ぶべきものとは到底考え難く、之こそが大いなる誤謬というべきものと考えざるを得ない。この点、字統では、「口という字は早くから用いられているが、卜文金文にその明確な用義例がなく祝禱の器の形である(サイ)との異同を確かめることはできない。」との解釈をしていることを考えても、「口」を「サイ」であると断定をすることは不可能のように思うのだが・・。
「口」の漢字データ
引用:「汉字密码」(P418、唐汉著,学林出版社)
「口」という文字は、象形文字でその形状は非常に単純で、容器以外考えようがない。形状から見ると、祝禱や固形物を入れるよりも液体を入れる容器のように思える。
しかし、わが国の漢字学の権威の白川静氏は、これをサイと呼び、祝禱を入れる器と解釈した。
氏は「従来の説文学において、口耳の口に従うと解するために字形の解釈を誤るものは極めて多く、古・召・名・各・吾などに含まれる「口」は全てサイと解釈すべきものを誤解したものだ」と喝破されている。しかし、私には、この単純な「口」という文字が、逆に、ほとんどがサイと呼ぶべきものとは到底考え難く、之こそが大いなる誤謬というべきものと考えざるを得ない。この点、字統では、「口という字は早くから用いられているが、卜文金文にその明確な用義例がなく祝禱の器の形である(サイ)との異同を確かめることはできない。」との解釈をしていることを考えても、「口」を「サイ」であると断定をすることは不可能のように思うのだが・・。
| 漢字「口」の楷書で、常用漢字です。 象形文字であり、甲骨から金文・小篆に至るまで、その文字の形体は一貫しておりいささかも変化が見られない。 この文字記号の生成から後世のかなり使い込まれた時代に至るまで、その形体上にほとんど変化が見られないということそのものが、この記号が時代を経ても一貫して同じ意味合いで捉えられていたというっ証左であり、一貫して「口」であり続けたのだ。 | |
| 口・楷書 |
| 口・甲骨文字 口の象形文字。 |
口・金文 口にしては口角が上がっており、液体を入れる容器のようにも感じられる。 |
口・小篆 甲骨・金文を引き継いでいる。これをサイと認識するには社会通念上の大きな変ぼうが必要である気がする。 |
「口」の漢字データ
漢字の読み
意味
同じ部首を持つ漢字 咽、員、右、唄、可、嚇、各、喝、喚、含、喜、器、吉、喫、吸、叫、吟、句、君、啓、古
漢字「口」を持つ熟語 口外、口蓋、口唇、口頭、悪口、陰口、口語、口誦、口説、口調、口座
- 音読み コウ、ク
- 訓読み くち
意味
- くち(飲食し、音声を発する器
- 入口、穴、港
- 量詞 例)一口、
同じ部首を持つ漢字 咽、員、右、唄、可、嚇、各、喝、喚、含、喜、器、吉、喫、吸、叫、吟、句、君、啓、古
漢字「口」を持つ熟語 口外、口蓋、口唇、口頭、悪口、陰口、口語、口誦、口説、口調、口座
引用:「汉字密码」(P418、唐汉著,学林出版社)
唐漢氏の解釈
「口」の形状は、まさに人や動物の口である。《説文》は「口」を解釈して、「人が話したり食べたりするところなり」。意味するところは、「口は人と動物が発声したり食べる器官である。
この為に「口」は食べたり話したりすることに関係する偏・旁の字に多い。「可、听、吟、号、咆」並びに吃、味、 吐、吮」等など。
「口」の形状は、まさに人や動物の口である。《説文》は「口」を解釈して、「人が話したり食べたりするところなり」。意味するところは、「口は人と動物が発声したり食べる器官である。
この為に「口」は食べたり話したりすることに関係する偏・旁の字に多い。「可、听、吟、号、咆」並びに吃、味、 吐、吮」等など。
漢字「口」の漢字源の解釈
象形文字:人間の口や穴を描いたもの。
象形文字:人間の口や穴を描いたもの。
漢字「口」の字統の解釈
人間の食。発声という行動は、基本中の基本であり、このことを言い表さずして人間のいかなる行動も表すことができないと考える。これが白川氏の主張に違和感を覚える最大の理由である。
- 象形文字「口の形」 説文に「人の言食する所以なりという。卜文・金文に見る字形のうち、口、耳の口と見るべきものはほとんどなく、概ね祝禱の器の形であるサイの形に作る。
- 従来の説文学において、口耳の口に従うと解するために字形の解釈を誤るものは極めて多く、古・召・名・各・吾などはみな祝禱の器を含む形。
- もっとも「口」という字は早くから用いられているが、卜文金文にその明確な用義例がなく祝禱の器の形である(サイ)との異同を確かめることはできない。
人間の食。発声という行動は、基本中の基本であり、このことを言い表さずして人間のいかなる行動も表すことができないと考える。これが白川氏の主張に違和感を覚える最大の理由である。
まとめ
漢字「口」は基本中の基本の言葉である。それだけに文明が高度になる前に、古代人の間では広く使われていたと考える。勿論最初は、象形文字というより、得に過ぎなかったかもしれない。文字を使って情報を伝達する高度な文明の前に、古代人たちはものをそのまま絵にかいて、相談をしたり、意思を伝えあっていただあろう。文字が最初から権力者たちの専有物であったと考えるのは妄想に過ぎなかったのではなかろうか。
漢字「口」は基本中の基本の言葉である。それだけに文明が高度になる前に、古代人の間では広く使われていたと考える。勿論最初は、象形文字というより、得に過ぎなかったかもしれない。文字を使って情報を伝達する高度な文明の前に、古代人たちはものをそのまま絵にかいて、相談をしたり、意思を伝えあっていただあろう。文字が最初から権力者たちの専有物であったと考えるのは妄想に過ぎなかったのではなかろうか。
| 「漢字の起源と成り立ち 『甲骨文字の秘密』」のホームページに戻ります。
|