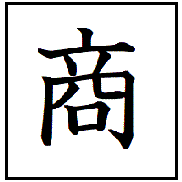漢字 商の成り立ちと由来から見えるもの:古代中国の中原で強国「商」を作り上げた荒ぶる殷商王朝が浮かび上がる
甲骨文字を最初に生み出し、強大な国家を作った殷の国は自らを「商」と呼んだ。
この商という国は今の中国の湖南省・安陽という年にその国家の礎を定め、自らを商と名乗る。
この商という名前そのものが、荒ぶる民族国家の成り立ちを物語るものである。
殷商民族は、兵器の製造に熱中し,南征北伐を愛した。
領土、人口、政権は国家の三要素をなす。ただし厳格に言えば「領土」とは武力コントロールあるいは占領下にある土地のことであり、「人口」とは武装統治にある民衆のことである。政権はすなわち武力を運用できる能力のある機構のことを言う。武力はあるもは専ら征伐を行使する常備武装のことをいい、国家の元である。
殖民統治に伴うもろもろの実践の中で、「国」の字は血なまぐさい洗礼の中で生まれた。現有実物の査証から甲骨文の記載からいうと、ただ「商」だけが国家の真の意味を表している。とうぜん漢字はその遺伝子の暗号で以ってさらにその形象をなし、さらにその真実をわれわれに告げている。殷商はつまるところいったいどのような国家だったのだろう。
商の時代は、生産技術はそれほど発達していなかったためか、国力の増強は専ら侵略による捕虜の獲得に頼ったのかも知れない。
「商」の漢字データ
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)
甲骨文字を最初に生み出し、強大な国家を作った殷の国は自らを「商」と呼んだ。
この商という国は今の中国の湖南省・安陽という年にその国家の礎を定め、自らを商と名乗る。
この商という名前そのものが、荒ぶる民族国家の成り立ちを物語るものである。
殷商民族は、兵器の製造に熱中し,南征北伐を愛した。
領土、人口、政権は国家の三要素をなす。ただし厳格に言えば「領土」とは武力コントロールあるいは占領下にある土地のことであり、「人口」とは武装統治にある民衆のことである。政権はすなわち武力を運用できる能力のある機構のことを言う。武力はあるもは専ら征伐を行使する常備武装のことをいい、国家の元である。
殖民統治に伴うもろもろの実践の中で、「国」の字は血なまぐさい洗礼の中で生まれた。現有実物の査証から甲骨文の記載からいうと、ただ「商」だけが国家の真の意味を表している。とうぜん漢字はその遺伝子の暗号で以ってさらにその形象をなし、さらにその真実をわれわれに告げている。殷商はつまるところいったいどのような国家だったのだろう。
商の時代は、生産技術はそれほど発達していなかったためか、国力の増強は専ら侵略による捕虜の獲得に頼ったのかも知れない。
| 漢字「商」の楷書で、常用漢字です。 「商」は、本は殷商民族が、自己の王国の都城の呼称としたものである。即ち「大邑商」(現在の河南省安陽の小さな村)である。商民族が自己の民族と国家の呼称であった。甲骨卡辞中の「今岁商受年。」然るに甲骨文の商の字の形象を見てみると戦争捕虜と関係がある。どうして戦争捕虜を押し込めておく場所に商朝の都城を選んだのか。どうして地名の商を殷商王朝の名称に合わせたのか? | |
| 商・楷書 |
| 商・甲骨文字 戦争で奪ってきた捕虜に入墨を入れ支配を明示した。その入墨の針器を台座の上に建て、祝禱と共に神に祈ることで、更なる侵略の成功を祈った |
商・金文 甲骨文字を承継しているが、経済を示す貝を付け加えることで、富の蓄積を誇ったのかも知れない |
商・小篆 小篆が使われる時代には商という国は消滅し、殷商人の末裔である商人か活躍した。 国名と一般名称の乖離 |
「商」の漢字データ
漢字の読み
意味
漢字「商」を持つ熟語 商人、商業、商売、商量、商事、商圏、商談、商団
- 音読み ショウ
- 訓読み あきな(う)、はか(る)
意味
- 品物を売買して利益を得る事(あきなう)、商売をすること
- 商売人、商人(あきんど)、「行商人」(例:隊商)
- はかる(良し悪しを明らかにする)
漢字「商」を持つ熟語 商人、商業、商売、商量、商事、商圏、商談、商団
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)
唐漢氏の解釈
甲骨文字の上部は軍の符号です。即ち「辛」の初文です。上古時期は捕虜を押さえつける刑具でもあった。下部は「内」の符号で、即ち丙の初文でもあった。それは地面に掘った軍の穴の牢獄の縦断面の図形である。甲骨文の後の一種の図形となり、また口を加えて地面の穴の入り口を示しこの種の牢獄の描写となった。
金文中の「商」の字は、甲骨文を受け継いでいるが、但し下辺に貝の字が付け加えられ商の字となっている。
約3300年前商民族は安陽の小さな村を捕虜を押し込めておく場所に選んだ。捕虜を押し込めておくために常備的な武装兵士を駐在させないわけにはいかない。軍事連盟の首領の商王は常備の武装兵士を指揮しコントロールするために移送させるわけにはいかない。このようにして事実上政治軍事の中心となった。捕虜中の工匠に対しては青銅の戈の上の図形文字には、飢餓と死亡の威嚇の下、必至に手工芸労働に専心し、兵器弓矢、玉器、精美を凝らした青銅器などを絶えることなく不断に製造することができたとき、大邑商は事実上王国の都城となった。
甲骨文字の上部は軍の符号です。即ち「辛」の初文です。上古時期は捕虜を押さえつける刑具でもあった。下部は「内」の符号で、即ち丙の初文でもあった。それは地面に掘った軍の穴の牢獄の縦断面の図形である。甲骨文の後の一種の図形となり、また口を加えて地面の穴の入り口を示しこの種の牢獄の描写となった。
金文中の「商」の字は、甲骨文を受け継いでいるが、但し下辺に貝の字が付け加えられ商の字となっている。
約3300年前商民族は安陽の小さな村を捕虜を押し込めておく場所に選んだ。捕虜を押し込めておくために常備的な武装兵士を駐在させないわけにはいかない。軍事連盟の首領の商王は常備の武装兵士を指揮しコントロールするために移送させるわけにはいかない。このようにして事実上政治軍事の中心となった。捕虜中の工匠に対しては青銅の戈の上の図形文字には、飢餓と死亡の威嚇の下、必至に手工芸労働に専心し、兵器弓矢、玉器、精美を凝らした青銅器などを絶えることなく不断に製造することができたとき、大邑商は事実上王国の都城となった。
漢字「商」の字統の解釈
商とは、辛と台座と口(サイ)に従う。辛は取っ手のある大きな針器。この入墨に用いる刑具を立てた、台座に祝禱を収める噐を据え付け、これに祈って神意を問う意であるから、商(はかる)ことを原義とする。古代王朝としての商は殷の正名でその都は大邑商といった。商はその神政的な支配を示す国号であったと思われる。
商は神意を計ることを原義とし、そこから商量の意が生まれ後通商の意となったものであろう。
商とは、辛と台座と口(サイ)に従う。辛は取っ手のある大きな針器。この入墨に用いる刑具を立てた、台座に祝禱を収める噐を据え付け、これに祈って神意を問う意であるから、商(はかる)ことを原義とする。古代王朝としての商は殷の正名でその都は大邑商といった。商はその神政的な支配を示す国号であったと思われる。
商は神意を計ることを原義とし、そこから商量の意が生まれ後通商の意となったものであろう。
まとめ
今我々が日常不断に使う「商」という漢字は、古代中国の「商」という国に由来する。この国は国名からして、血塗られた侵略と構想のの中で生まれ育った。人類は、このようにして戦いと侵略の歴史を繰り返してきた。それから後の生産力の高揚と相まって、血なまぐさい戦争の繰り返しから脱して、平和に生活することが出来るようになった。我々はこの人間の歴史からともに共存するという生活様式・生き方を今後とも大切にしなければならない。
今我々が日常不断に使う「商」という漢字は、古代中国の「商」という国に由来する。この国は国名からして、血塗られた侵略と構想のの中で生まれ育った。人類は、このようにして戦いと侵略の歴史を繰り返してきた。それから後の生産力の高揚と相まって、血なまぐさい戦争の繰り返しから脱して、平和に生活することが出来るようになった。我々はこの人間の歴史からともに共存するという生活様式・生き方を今後とも大切にしなければならない。
| 「漢字の起源と成り立ち 『甲骨文字の秘密』」のホームページに戻ります。
|