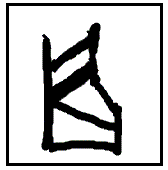漢字の成り立ちは何を物語るか:漢字・骨は肉(月)交じりの残骨をいう。甲骨文字は部分を繋ぎ合わせた形をしていて、古代人がバラバラのものを繋ぎ合わせたものとして認識していたことが字から分かる
「骨」の漢字データ
引用:「汉字密码」(P452、唐汉著,学林出版社)
| 漢字「骨」の楷書で、常用漢字です。 人間や脊椎動物の骨格を表す。拡張され、全体の細かいことや飾りを除き、基本的な構成部分をいう。 | |
| 骨・楷書 |
| 骨・甲骨文字第1款 骨同士を連関し支え合っている様 |
骨・甲骨文字第2款 牛の肩甲骨の形という |
骨・古文 >肉(月)と関連し合っていることを示した |
骨・小篆 古文を引き継いでいる。 |
「骨」の漢字データ
漢字の読み
意味
同じ部首を持つ漢字 骨、滑
漢字「〇」を持つ熟語 遺骨、骸骨、骨格、骨組
- 音読み コツ
- 訓読み ほね
意味
- ほね(脊椎動物の体内で身体を支える基本部分)
- からだのの組み立て、
- 体の構成の基本的な部分
同じ部首を持つ漢字 骨、滑
漢字「〇」を持つ熟語 遺骨、骸骨、骨格、骨組
引用:「汉字密码」(P452、唐汉著,学林出版社)
唐漢氏の解釈
「骨」原本は象形文字である。甲骨文の骨は二つの款があり、その一つは骨が互いに支えあっている様子、その2款目は既に修理された、牛の肩甲骨の形だ。
古文の「骨」の字は将に甲骨文字の省略で、下辺に一個の「肉」の字を加えて、骨や肉に関係がありか包含したことを示している。小篆以後は変化し、既に大きな変化はないが、脈絡は通じている。
「骨」原本は象形文字である。甲骨文の骨は二つの款があり、その一つは骨が互いに支えあっている様子、その2款目は既に修理された、牛の肩甲骨の形だ。
古文の「骨」の字は将に甲骨文字の省略で、下辺に一個の「肉」の字を加えて、骨や肉に関係がありか包含したことを示している。小篆以後は変化し、既に大きな変化はないが、脈絡は通じている。
漢字「骨」の字統の解釈
会意文字:冎と肉(月)とに従う。冎は残骨の形。肉を伴っているので、もと骨交じりの肉をいう語である。説文に「骨は体の質なり、肉の核なり」というのが分かりやすい。
会意文字:冎と肉(月)とに従う。冎は残骨の形。肉を伴っているので、もと骨交じりの肉をいう語である。説文に「骨は体の質なり、肉の核なり」というのが分かりやすい。
まとめ
甲骨文字の骨は非常にシンプルに、数少ない線で構成され、本質的な見方をしていた気がする
甲骨文字の骨は非常にシンプルに、数少ない線で構成され、本質的な見方をしていた気がする
| 「漢字の起源と成り立ち 『甲骨文字の秘密』」のホームページに戻ります。
|