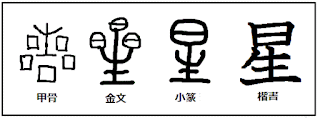星:数多くの粒粒の光が木にぶら下がっていると古代人は見た
夜空にきらきら光る星を古代の人はどう見ていたのでしょう。結晶が散らばってきらきら輝いていると見た人もいるでしょうし、夜空に輝く星はまるで生き物のように見え、大きな木にいっぱいの輝く光の粒が植わっているように見えたのかもしれません。
随分ロマンチックな見方をしていたのかもしれません。そのような見方は現代人もそれほど大きな違いはないのですが、ある種ほっとする部分もあります。
「星xing」は、通常、夜空の小さな明るい星を指します。甲骨文字の「星」という言葉は会意文字です。
古代の人々は5つの円(ナイフの都合で四角形に変更)を使用して夜空の多数の星を表し、「生」を用いてその発音と意味を表すために使用されました。
古代の祖先の目では、時には多く時には少なく、空の星は明るかったり暗かったり、それに流星は空を横切ることがよくあり、それらはきっと植物のようであるに違いない、成長および繁殖ができるものだろうと見えたのだろう。だから「星」という単語は「5つの粒の星」と「生」との会意文字です。
金文の「星」という言葉は、すでに変異を生じ3つの「日」に変わっています。ここでの「日」は小さくて光沢のある星、「3」はたくさんの意味です。 小篆の「星」は金文に似ています。
説文の解釈
説文は「量」と解釈し、晶と生の声から、一日の象形としました。「許慎は誤って「星」を量の造字法の帰結の象形と誤まって認識しましたが、これは彼が甲骨文字を見たことがなかったからです。しかし、彼は「星」は「量」簡略化と考えたのは正しい。
字統の解釈
正字は晶に従い、声符は生。説文に「万物の精、上りて列星となる」という。もと玉光の星星たるをいう。卜文に晶を星の字を用い、時に生声を加えているものがある。
漢字源の解釈
会意兼形声。「きらめく三つの星+音符生」で。済んで清らかに光るほし。「生」は生え出たばかりのみずみずしい芽の姿。
結び
夜空に輝く星は、われわれにある種の希望をもたらし、時には導きの星として明るい希望を尾もたらすものであったのですが、科学の発達の前に、輝く星もごつごつの岩の塊であったことが分かり、ある種の幻滅を感じさせてしまうとこともありました。
しかしこれは科学が悪いのではなく、表面だけしかものを見ない人間の欲であるかも知れません。ごつごつのイワの塊が、この宇宙に生まれ、キチンをした物理法則に従って運動を続けていること自体ロマン以外何者でもないでしょう。
| 「漢字の起源と成り立ち 『甲骨文字の秘密』」のホームページに戻ります。 |