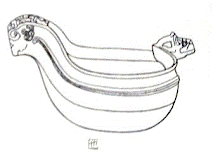漢字・師:元々軍用語!やがて先生の意も持つように。一体なんで?
この記事は以前にアップした下記の記事を全面的に加筆修正したものです。
漢字「師」の成り立ちから読めるもの:この漢字は最初から戦闘集団を表していた。
導入
全国の学校で卒業式が行われている。一昔前の卒業式では必ず「仰げば尊し我が師の恩」のようなフレーズの歌が流されていた。
ところが最近では、学校の教師と生徒の関係がフラットになって、まるで友達のような会話が見られる状況では、「我が師の恩」などというフレーズは流されないのではなかろうか。
実はこの「師」という言葉の意味も随分異なって来ている。
この字は生まれた当初からしばらくは軍隊の戦功祈願の儀式を表す言葉であって、その名残りが「師団」という軍隊用語に残されていた。
前書き
目次
**********************
漢字「師」の今
漢字「師」の成立ち
漢字「師」の由来:出陣に際し、祭肉を祖先の廟に祭って戦功を祈願した事に起源がある
軍の戦闘集団を師団といい、(日本の戦時の師団の構成人数は大体2万程度の兵力でした。)その指揮者を「師」というようになった。
しかし、古代国家の軍隊はその経済力から類推ししても、せいぜい1000人規模でなかったかという説もあります。少なくとも人口10万人規模の国家でないと軍隊を擁するにも一苦労であったことでしょう。その意味で、この言葉が本当に確立されたのかも疑わしいのですが、そこそこの規模の軍隊を擁するのは周も末期になってからそれも春秋戦国時代に入ってからであろうと推察されます。因みに春秋時代の総人口はせいぜい500万人前後だったろうと言われています。
| 漢字「師」の楷書で、常用漢字です。 昔から2500人の師団を表すこと定着していたようだ。 あるいはこの漢字一字で、軍を表したり、いくさ(戦争)を表すようだ。 漢字「師」の左側は、甲骨文や金文では启で祭肉を表していた。ところが小篆では、神梯に変化している。なぜか。国家の規模が大きくなり、軍隊の規模も大きくなり、軍隊もさらなる神格化が必要になったと考えられる。したがって、今まで祭肉をシンボル的に使用していたが、もはやそれでは人々を引き付けられなくなり、神を持ち出したのではないだろうか。即物的な祭肉より、神梯からの神の降臨を演出ことで権威付けを強めたのではなかろうか。 | |
| 即・楷書 |
| 甲骨文字や金文の左側の記号は「祭肉」を表してた。ところが小篆では神梯を表すという。その変化は、軍の行動により神格化が求められた結果ではないだろうか。 | |||
| 師・甲骨文字 軍が出行するとき、戦功を祈って祈願する時の祭肉を表す |
師・金文 甲骨文字を引き継ぎ、軍の出行の際の祭肉を軍刀に突き刺し出陣すること |
師・小篆 金文を引き継ぐが、祭肉が神梯に変化し、より神に祈ることを明確にしたものか |
「師」の漢字データ
- 音読み シ
- 訓読み いくさ
意味
- 軍隊 二千五百人の軍の隊のことを言った。 説文に「二千五百人を師と爲す。币に從ひ、𠂤に従ふ。官の四币なるは、衆の意なり」とある。
- 人を教え導く人、先生 例 師匠
- 先生として尊敬する、手本とする (例:恩師)
漢字「師」を持つ熟語 師団、恩師、師匠、軍師、師走
**********************
漢字「師」成立ちと由来
参考書紹介:「落合淳氏の『漢字の成立ち図解』」
字統の解釈
启と帀に従う。启は軍の出行のとき携える祭肉の形で、師の初文。帀は把手のある曲刀の刃の部に小さな叉枝のあるもの。軍の出行するときは祖先の廟や軍社などに祭って、神佑を祈りその際肉を携えて出行するが、途中で軍を分遣して行動するときは、その際肉を分って出発させる。
漢字「師」の民俗的解釈
遠くからやってきて、腰を下ろし、休憩することを表す。しかし、唐漢氏は、文字の変遷の中で、祭肉が神梯に変化していることを説明しているが、この変化は実に重要で、軍の組織の中に、強大化するにつれ、一層の神格化・権威化が持ち込まれたことを示しており、軍の組織がここで、画期を成す変化を生じたものと考えられよう。
「師」古代漢語P63 王力編、高等学校教材
- 軍隊で2500人で一師を構成する。一般に漠然と軍隊を指す。
- 知識を授ける技術人、先生。(弟子に相対する)
- 楽官 上古の楽師は一般的に盲目の人を任命していた。
「師」の歴史的変遷
文字学上の解釈

ト辞では𠂤は師の左の要素であるが、古代中国で、出陣の際に祖先に戦勝を祈願する儀式に使われた「肉」を表していた。師はその肉を分ける刀を表す「帀」と肉からなる。
以下、軍の用語が先生という意味を持つようになった歴史的過程といきさつを纏めます。
- 軍事的な起源 「師」の甲骨文や金文からは、軍隊や戦争に関わる意味が盛り込まれていると見られます。 古代中国では、出陣の際に祖先に戦勝を祈願する儀式が行われ、その際に祭肉を供えることがありました。 軍隊を指す言葉としての「師」は、主に「大規模な軍隊(約2500人)」を指しました。戦の指導者や統率者も「師」と呼ばれました。
- 転じて指導者の意味へ 戦場で軍隊を率いる指揮官は、兵士たちを導き、教育・訓練を施しました。この役割から、「師」は指導者や教育者を意味するようになります。 軍隊の統率者が戦術や戦略を教える存在だったことが、知識や技術を教える一般的な指導者の意味へと広がりました。
- 儒教と教育の影響 儒教が広まると、知識や道徳を教える役割を担う者も「師」と呼ばれるようになりました。 孔子のように弟子を持って教え導く者が「師」と称され、学問や道徳を教える先生の意味が確立しました。
- 官職名としての「師」 古代中国では「太師」「少師」など、教育や政治の顧問的役割を持つ官職も存在しました。これは、指導的役割を重んじた文化を反映しています。

字統では、師の変遷について、以下のように説明している。
師長には古く氏族の長老たるものがあたり、師氏と称した。現役を退いたのちは、氏族の指導者 として若者の育成にあたり、師職となる。(周礼)に多く残されている師系の官職は、氏族時代におけ る師の職業のなごりを、その退化した形式において 伝えるものである。師のありかたの推移は、古代氏 族国家のありかたの推移を反映している。
まとめ
「師」は、元々軍を率いる指導者を指していましたが、その指導力が教育や学問の分野にも適用されるようになり、現代の先生という意味へと発展したのです。
以上のように、漢字「師」は実に多くの変遷を遂げ、それだけ多くの異体字を持っているようである。この事実は、この漢字が、軍隊に使われ、軍隊の仕組みやありかたが、変化するのに応じて、変化してきたことを示している。
| 「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。
|