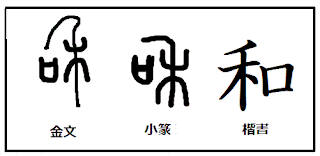人は如何に「きこえる」レベルから神に近いレベルの発話者の話を傾聴する「聖」にまで到達したのか
前回、漢字「聖」が聞や聴と同じ一つの系統に属することを知り、目からうろこの感じがしたのだが、今回はその「聖」に焦点を当て、聖の成り立ちや由来に迫ってみよう。
話変わって、11月11日はキリスト教徒では特別の日で、【万聖節】というのだそうで、そのことが毎日新聞のコラムに掲載されていたので、引用する。
第826回 「毎日ことば」 解説
きょうが特別な日
ばんせいせつ【万聖節】 キリスト教 で聖人たちを記念する祝祭。この場合の万 は「全ての」、節は「特別な日」との意味 です。「諸聖人の祝日」などともいい、カトリックでは11月1日。
ハロウィーンはその前夜祭ですが、日本ではそちらが有名に。
https://salon.mainichi-kotoba.jp
導入
前書き
目次
**********************
漢字「聖」の今
漢字「聖」の解体新書
| 漢字「聖」の楷書で、常用漢字です。 | |
| 聖・楷書 |
| 「きく」ことを表す漢字であるが、只きこえることを表す漢字「聞」から出発し、拝聴するの「聴」を経由し、神に近いレベルにまで達した人間の話にききいる「聖」までの変化をよく見ていただきたい。 | |||
| 聞・甲骨文字 |
聴・金文 |
聖・小篆 |
「聖」の漢字データ
- 音読み セイ、ショウ
- 訓読み ひじり
意味
- 物事の筋道を立てて、偏ってなく、高潔である状態
- 清らかな。汚(けが)れがない。美しい。濁った所がない。透き通っている (聖域)
- 天子(国を治める最も地位の高い人)。また、天子に関する物事の上に付ける語」(例:聖断)。
- 詩人・杜甫のことを詩聖と呼びます
異体字 琞、垩
同じ部首を持つ漢字 聞、聡、聲、職
漢字「聖」を持つ熟語 聖、聖断、聖域、聖人
**********************
漢字「聖」成立ちと由来
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)唐漢氏の解釈
甲骨文の形は、人が耳を立てて人の教えを注意深く聞いているようなもので(耳の下に「口」があります)、聞いたことをはっきりと話す、つまり「聞く」という意味とも取れます。わかりやすく、わかりやすく説明すること。 金文は甲骨文から引き継がれていますが、「耳」の下の人型がわずかに変更されています。
小篆書の形は、「耳から嘉文へ」という意味に進化しました。小篆書の全文。楷書の口は壬の音から来ています。「壬」はここでは口と耳の間を「通過する」という意味です。 そのため、楷書は「聖」と書かれ、現在は「圣」となっています。
漢字「聖」の字統の解釈
会意 旧字は耳と王と口とに従う。耳と王とは耳 を強調した人の形。壬は呈(呈)・逞・望(望)の字の従うところで、人のつま先立ちする形。口は、サイ、祝禱を収める器である。
聖は祝稿して祈り、耳をすませて神の応答するところ、啓示するところを聴くこ とを示す字で、聽(聴)の従うところも聖と同じ。
聞の卜文も、人の上に耳をかく形である。祝祷し 神の啓示するところを聞く者はその神意にかなうものとされた。
漢字「聖」の漢字源の解釈
会意兼形声。壬は、人が足をまっすぐのばしたさま。呈 は、それに口をそえて、まっすぐ述べる、まっすぐさし出すの意を示す。聖は「耳+音符呈」で、耳がまっすぐに通ること。わかりがよい、さといなどの意となる。
漢字「聖」の変遷の史観
文字学上の解釈
字統の説明《聖は西周期の金文にみえ、〔班段〕「文王王の聖孫」、〔師望鼎〕「王、聖人の後を忘れず」、〔師詢段〕「乃の聖なる祖考」のように、その家系を尊んで特に聖の字を加えている。 また〔史牆盤〕「憲聖なる成王」と、その徳を讃して聖武・哲聖のようにもいう。本来は聖職者をいう 語であったものが、ひろくその徳性をいう語となり、 西周後期にはすでに多くの人に用いられる語であったらしい。(紀元前1100年頃 - 紀元前771年:筆者)
〔詩、小雅、正月〕に「具予をば聖なりと謂ふも誰か鳥の雌雄を知らんや」の句がある。 人はみな、自ら聖と称してはばからなかったのであろう。》
といっても始皇帝の中国統一に先立つこと500年まさに戦国時代の真っただ中、群雄が覇を争っていた時代である。群雄の覇者は自らのアイデンティティーを求めて苦労していたが、その一つに軍事的な力以外に拠り所の一つとなった概念であったのかもしれない。
そしてついにこの概念を哲学的な体系の中に組み込んだのが孔子であった。ここまで考えると漢字「聖」という言葉一つにしても、それなりの歴史的背景を担っていたのだという感慨を受ける。
まとめ
ただきこえることを表す漢字「聞」から出発し、拝聴するの「聴」を経由し、神に近いレベルにまで達した人間の話にききいる「聖」まで後付けてきた。聞くという行為だけでも、発話者の権威を高めることの背景に社会の階級分化が事が伺える。この間、約1000年の時間的経過を経ている。文字の変化が歴史的時間経過に必ずしも同期するものではないが、おおざっぱな歴史的経過をたどるには役に立つのかも知れない。| 「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。
|