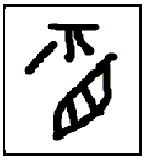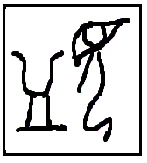漢字「見」成立ちと由来に見る人間のさまざまな見方
「みる」という行為に関する漢字:見、望、看、視、監、省、臨、観
「みる」という行為を表す漢字は実に多い。その多さは見るという行為一つとっても、実に多くの見方があった。その事実は人間の社会は太古の昔から、すでに実に複雑な社会でなかったかと想像される。実は我々が考えていた以上の多様性を持った社会の姿が浮かび上がってくる。
「みる」の漢字
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)
漢字「〇」を含む故事、成語、ことわざ ☜ については、こちらが詳しいです
「みる」という行為に関する漢字:見、望、看、視、監、省、臨、観
「みる」という行為を表す漢字は実に多い。その多さは見るという行為一つとっても、実に多くの見方があった。その事実は人間の社会は太古の昔から、すでに実に複雑な社会でなかったかと想像される。実は我々が考えていた以上の多様性を持った社会の姿が浮かび上がってくる。
| 漢字「見」の楷書で、常用漢字です。 望見を望といい、跪いて見るを見という。 あなたは見る、看る、視る、観る そして、監、望、省、臨、観の違いは判りますか。 | |
| 即・楷書 |
| 見・甲骨文字 跪いて見ること。見るという行為は相手に向かって霊的な交渉を持つことを意味する |
望・甲骨 立ち上がって遠くを見ている |
看・小篆 上部に「手」+下部「目」 |
視・甲骨 示(祭卓)+見:神の降臨 |
| 監・甲骨文字 水盆+跪いた人で構成される |
省・甲骨 眼の上に三画を付け加えて、目に差し込む光を左右から観察している形 |
臨・金文 一つの大きな眼が地上の3つの小さなものを俯瞰している様子 |
観・甲骨 鳥の形であることから、鳥占いの方法による儀礼に関する文字 |
「みる」の漢字
見るという意味を持つ漢字のあれこれ
- 見・・・見るの本義は見届けること
- 望・・・人が足をそばだてて遠く望む形
- 看・・・手を額にかざして遠くを見ることを意味します。手を目の上にかざして望見ることを言う
- 視・・・本義は調べるように見る、細かく見るの意味である。
見えているという状態をいうのではない - 監・・・水盤に映った自分の姿を細かく見ている。監は拡張され、別の人を観察する、あるいは別の物を観察することに拡張された。
- 省・・・細かく見て、じろじろ観察する
- 臨・・・象を取り前に進め、地上の細かい物体を細かく観察することです。、降臨の意を基本的に重ねて持つことになりました。
- 観・・・説文に「諦視するなり」とあって、審らかに観る意とするが、農耕儀礼に関する字と思われる。
- 「視、看、見」の三字はすべて、"瞧"の動作である。但し、「視、看」の二字は結果に及ばないで、「見」は結果を示している。即ち、看たけれど、見えなかったという言い方ができる。「見」は見えた、認識したという結果まで言及する
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)
唐漢氏の解釈
「みる」という行為の基本的な漢字は、「見」である。見は視ると異なり。見るの本義は見届けること、発見することである。
「みる」という行為の基本的な漢字は、「見」である。見は視ると異なり。見るの本義は見届けること、発見することである。
漢字「見」の漢字源の解釈
会意文字である。「目+人」 目立つものを人が目ににとめること。 また目立って見えるものという意から現れるの意を持つ
会意文字である。「目+人」 目立つものを人が目ににとめること。 また目立って見えるものという意から現れるの意を持つ
漢字「見」の字統の解釈
象形文字:目を主とした人の形。 望見を望といい、跪いて見るを見という。 謁見の見は儀礼の時の姿である。見るという行為は相手に向かって霊的な交渉を持つことを意味する。
象形文字:目を主とした人の形。 望見を望といい、跪いて見るを見という。 謁見の見は儀礼の時の姿である。見るという行為は相手に向かって霊的な交渉を持つことを意味する。
まとめ
「みる」という単純な行為一つとっても、実に多くの見方があった。その事実は人間の社会は太古の昔から、実は我々が考えていた以上の多様性を持った社会の姿が浮かび上がってくる。
「みる」という単純な行為一つとっても、実に多くの見方があった。その事実は人間の社会は太古の昔から、実は我々が考えていた以上の多様性を持った社会の姿が浮かび上がってくる。
漢字「〇」を含む故事、成語、ことわざ ☜ については、こちらが詳しいです
| 「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。
|