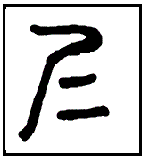漢字「残」の成立ちと由来:「歹」(動きの取れない脚+「戔」二つの戈(ほこ)からなる。激しい戦闘で傷つき動きの取れない状態を示す
漢字「残」の成立ちと由来:「歹」(動きの取れない脚)+「戔」二つの戈(ほこ)からなる。激しい戦闘で傷つき動きの取れない状態を表しています。
2022年2月5日から北京でオリンピックが開かれる。中国語で奥运会という。また3月4日金曜日~3月13日日曜日の10日間パラリンピックが開かれる。このことを中国語で『残疾人奥运会』という。
パラリンピックの中国語訳はどうもしっくりこない。日本でいうと廃疾者であり、完全な差別用語のような気がする。なぜオリンピック委員会は異議を唱えないのか不思議た。あれほど人権人権と騒ぎ立てるにもかかわらず、このような呼び名をそのままにしておくとは。
もちろん中国語を日本語で解釈することはできませんが、少なくとも、中国語を中国人自身がいかに解釈しているかを深く話し合いすべきだと考えます。
「残」の漢字データ
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)
漢字「〇」を含む故事、成語、ことわざ ☜ については、こちらが詳しいです
漢字「残」の成立ちと由来:「歹」(動きの取れない脚)+「戔」二つの戈(ほこ)からなる。激しい戦闘で傷つき動きの取れない状態を表しています。
2022年2月5日から北京でオリンピックが開かれる。中国語で奥运会という。また3月4日金曜日~3月13日日曜日の10日間パラリンピックが開かれる。このことを中国語で『残疾人奥运会』という。
パラリンピックの中国語訳はどうもしっくりこない。日本でいうと廃疾者であり、完全な差別用語のような気がする。なぜオリンピック委員会は異議を唱えないのか不思議た。あれほど人権人権と騒ぎ立てるにもかかわらず、このような呼び名をそのままにしておくとは。
もちろん中国語を日本語で解釈することはできませんが、少なくとも、中国語を中国人自身がいかに解釈しているかを深く話し合いすべきだと考えます。
| 漢字「残」の楷書で、常用漢字です。 左の部分は「歹」、右は「戔」で両形の会意で激しい戦闘で傷を負って動けなくなった状態を示しているとされます。 このように元々は「廃疾」のように使われていたのかも知れませんが、後世の使われ方は、いわゆる「残る・残留・残滓」という意味に使われているようです。 | |
| 残・楷書 |
| 残・甲骨文字 上と下の2つの「戈」の形をしており、兵の刃で近接して互いに殺戮の戦いの意味を示しています。 |
残・金文 甲骨文字を引き継いでいますが、戈がより明示的になっています |
残・小篆 左の部分は足を緊縛され、動きが取れないことを示しています |
「残」の漢字データ
漢字の読み
意味
同じ部首を持つ漢字 死体、
漢字「残」を持つ熟語 残虐、残酷、残念、残渣、残像、
- 音読み ザン
- 訓読み のこ(る)
意味
- そこなう ・・「殺す」(例:残骸)
傷つける、切る・切断
壊す 破る - 傷・痛み
- 酷い、むごい
同じ部首を持つ漢字 死体、
漢字「残」を持つ熟語 残虐、残酷、残念、残渣、残像、
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)
唐漢氏の解釈
「戔」は「戋」の繁体字です。 「戔」は「残」の本字でもあります。甲骨文字の「最初の」キャラクターは、上と下の2つの「戈」の形をしており、兵の刃で近接して互いに殺戮の戦いの意味を示しています。
「戔」は「戋」の繁体字です。 「戔」は「残」の本字でもあります。甲骨文字の「最初の」キャラクターは、上と下の2つの「戈」の形をしており、兵の刃で近接して互いに殺戮の戦いの意味を示しています。
漢字「残」の漢字源の解釈
会意兼形声:「戈+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。残は「歹(ほね)+音符」で小さく切りとって、小さくなった残りの骨片
会意兼形声:「戈+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。残は「歹(ほね)+音符」で小さく切りとって、小さくなった残りの骨片
漢字「残」の字統の解釈
旧字は残につくり、戔声。戔に浅小軽薄のものの義があり、残とは残骨・残片の意である。「説文」に賊と人を害する残賊の義とする。
旧字は残につくり、戔声。戔に浅小軽薄のものの義があり、残とは残骨・残片の意である。「説文」に賊と人を害する残賊の義とする。
まとめ
会意文字であるようだが、甲骨文字にせよ、金文にせよ、まるで象形文字であるかのように生き生きとした人々の姿が描写されている。文字の形に簡略化し、無駄を省いたデッサンとなっており、実に素晴らしい記号化、抽象化がなされていると思う。
会意文字であるようだが、甲骨文字にせよ、金文にせよ、まるで象形文字であるかのように生き生きとした人々の姿が描写されている。文字の形に簡略化し、無駄を省いたデッサンとなっており、実に素晴らしい記号化、抽象化がなされていると思う。
漢字「〇」を含む故事、成語、ことわざ ☜ については、こちらが詳しいです
| 「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。
|