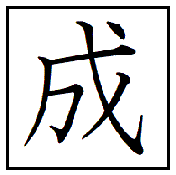漢字・成の成立ち:戈と丁からなる
漢字・成の成り立ちと起源:古代の武器で、戦いに際してお祓いや祈願を込めて飾りをつけた戈
古代中国の「秦」の宰相であった、李斯が《谏逐客书》の中で、『秦成帝业』(秦は帝業をなす・・・秦国は統治の大業を完成させたの意味)といったのが「成」の最も典型的な使い方であったのかも知れない。
|
|
漢字「成」の楷書で、常用漢字です。
成立ち:武器であった「戈」と「丁」からなり、丁で打ち据えて、治める、まとめて統一するという意味です
- なる 完成する
成り立つ、ある状態に達する
- なす、 成し遂げる 成就する
- 平らげる 平定する、征服する
などの意味があります
|
| 成・楷書 | |
漢字「成」を含む成語、ことわざ
- 既成事実:社会的に広く行われていたり、広く存在している事柄
用法: 既成事実化している
- 画虎不成:後漢の将軍馬援が子馬厳、馬敦の子供たち兄弟に宛てた手紙の中で、二人が遊侠に走ることに対して、「虎を画いて成らず帰って犬に似てしまうような、素質のないものが優れた人のまねをして軽薄に振舞うようなことがあってはならない。」と戒めた。
- 既成概念:社会的に広く認知されている考え
- 故事成語
- 心願成就:心の中で神仏に念じたり、自分に強く誓った願いが叶うこと
自分が強く願わなければ叶わないという戒め
- 大願成就:大きな願いが成し遂げられたこと
- 大器晩成:大きな器は完成するまでに時間がかかることから、大人物となる者は、世に出て大成するのが遅いという意味。大人物でもない人間が、自分はいつか世に出ると自分を慰撫する言葉
出所:先秦·李耳《老子》:“大器晚成,大音希声。”
- 老成円熟:経験豊富で、物事によく通じ、人格穏やかで、円熟味を持った人を指す
- 墨守成規:頑なに規則を固守すること、戦国時代墨子が城を守り通したことの故事があるが、墨子は守る戦術は実に柔軟で、それは現在のゲリラ戦術にも通じる
- 即身成仏:生きたまま究極の悟りを開き、仏になることを「即身成仏」という。日本では密教に多く見られ、ミイラ化した高僧が祀られている寺が多く存在する。最も有名なのは、鉄門海上人です
- 朝成暮毀:物事を頻繁に作ったり壊したりすること。朝令暮改にも通じる
|
|
|
|
成・甲骨文字
武器の戈に神聖なる飾りをつけた神聖なる武器を表す |
成・金文
文字として形がより整備され、洗練されている |
成・小篆
丁は打って一つにまとめる意味を有する
文字自体が進化したのでは?
金文の時代には「まとめる」という意味は持っていなかった |
「成」の漢字データ
漢字の読み- 音読み セイ、ソン、ジョウ
- 訓読み な(る)な(り)
意味
- なる 完成する
成り立つ、ある状態に達する
実る 例:成熟する、実がなる
- なす、 成し遂げる 成就する
- 平らげる 平定する、征服する
- 将棋で、①敵陣に入った場合、②敵陣内で動いた場合、③敵陣から外に出た場合に「成る」ことにより、駒がバージョンアップする
玉と金は成ることはできません。
残る小駒の銀、桂、香、歩は成ると、金と同じ動きになります。
角と飛車は駒本来の動きに合わせ、王将を同じ動きをすることができます
同じ部首を持つ漢字 成、城、盛、幾、誠、鉞
引用:「汉字密码」(Page、唐汉著,学林出版社)
唐漢氏の解釈
成の字の本義はまさかりです。甲骨文字の右の上部は長柄の斧である。
金文中の「成」の字の中で、右辺の曲がった大鉈が更に形が変化し、武器であることが協調されている。
小篆の変化は比較的大きく、上辺の斧の形が変化して鉞となって、下部の長い縦線が変化し一個の丁の字(下に叩き切ってしかる後持ち上げることを表示している。)即ち漢字は小篆の時代に丁という意味が加わったことで、変化したのではなかろうか
楷書では書くときに丁の字は横に湾曲して現在の「成」の字となった。
漢字「成」の漢字源の解釈
会意兼形声:丁は打って一つにまとめる意味を有し、「打つ」の原字。「成」は戈+丁でまとめ上げる意を含む
漢字「成」の字統の解釈
戈と丨(コン)とに従う。戈の下に記すものは丨(コン)、列国期のものには、これを戈身にかけた形に作るものがあり、その製作が終わった時に、そのスイ飾を加えて祓ったもので、それで初めて成就の意味のとなる。
まとめ
会意文字であるようだが、甲骨文字にせよ、金文にせよ、まるで象形文字であるかのように生き生きとした人々の姿が描写されている。文字の形に簡略化し、無駄を省いたデッサンとなっており、実に素晴らしい記号化、抽象化がなされていると思う。