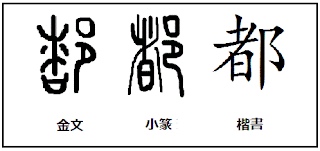漢字「俞」と「盗」の違いは?
中国の笑い話に「牛泥棒」というのがある。これはNHKの中国笑話選という中国語教材に掲載されていたものですが、今日はこれを紹介しながら、漢字に迫って行きたいと思う。
昔々ある時、一人の男が道端に首枷をハメられてうずくっていた。とぼけた話ですが、ここに出てくる、泥棒は中国語では、「小偷」というのですが、今日はこの「小俞」の「偷」について、お話したいと思います。
たまたまその時、男の友人が通りかかって、男を見て驚いて尋ねた。
「お前は一体何をしたんだ。そんなに首枷をハメられ、どんな悪いことしたんだ?」
男は自嘲気味に答えた。「実は、道端に縄の切れ端が落ちていて、それを家に持って帰ってしまったんだよ。」
友人を驚いて尋ねた。「たったそんなことで、なんで首枷までハメられるんだ。何か他に大きなことをしたんじゃないの。」
男はそれに答えていうには、「実はその縄の先に運が悪いことに牛が一頭繋がっていたんだよ」
漢字の成り立ちからいうと、この「偷」という漢字は、人偏+「俞」で俞をする人という成り立ちになります。字面通りいうと「中を抜く人」とでもいうのでしょうか。
一方同じ意味で「盗」という漢字がありますが、こちらの方は、「お皿の食べ物によだれを垂らす」様を表現した漢字ということです。これについては、後日改めて取り上げたいと思います。
ということで、ここではまず「俞」の成り立ちから。
引用:「汉字密码」(P756、唐汉著,学林出版社)
「唐漢」さんの解釈"俞"、これは会意字です。甲骨文字の下の部分は船の絵文字で、小船の象形文字です。上の部分の三角形の符号は、前進を意味します。
金文の「俞」では左側は「ボート」ですが、上の三角形は右に移動し、併せて縦長の曲線は前方へのセーリング(反対側に川を渡る)の意味を強調しています。小篆の "俞"の字は、まさに前に行く符号が2つに分割し、前の三角形は上部に移動し、下部の長い曲線は "水を行く様を表している。楷書では水貌が立刀に変化したことを示している。
漢字源
会意文字である 左に 船を右にこれにくりぬく刃物の形を添えたもの 「説文解字」に 木を中空にして船と為すなり」とある。偷(抜き取る→盗む)・癒(病根を抜き取る)。踰(中間の段階を抜いて進む→越える)、輸(物を抜き取って車で運ぶ)などの音符として含まれ、抜き取るという意味を含む。
熟語では、「愉悦」という言葉がありますが、セックスなどで、気持ちが良くなり、「心(リッシン偏)+俞(中身がない)」(心が抜けた)状態を言うのかもしれません。
こうして考えると、「偷人」(他人の男を寝取った人)と「盗人」(盗んだ人、泥棒)の違いが、納得できますね。
字統の解釈
会意文字。船と俞に従うとあります。 字統では「手術用の取っ手のある大きな針」としています。
この針で膿血を番に写し取るのである金文の字型は針の横に斜線が入っているが、これは膿血を盤に移すことを示すことによってその患部が治癒するので、膿が取り除かれ傷が癒され心が休まる事をいう。
後書き
漢字のルーツを読み解くというのは、非常に難しい。このページでも挙げた、唐漢氏、藤堂先生、白川先生の3人のご意見もてんでばらばらだ。言い出したものが勝ち、いいたい放題みたいに感じてしまう。しかしそれだから面白い。このページで掲げた「俞」を旁とする漢字でも「瑜喻渝榆谕愉諭輸踰」が、たちどころに上がって来ます。これらの漢字から、「共通する」意味を抽出し、成り立ちに迫る態度が望まれるのでしょう。
| 「漢字の起源と成り立ち 『甲骨文字の秘密』」のホームページに戻ります。
|