導入
トランプにはもう我慢ならん!!
アメリカは三度核を使った。地球を破滅させる気か!
今回のイランの核施設攻撃は本質的には広島・長崎と同じことだとうそぶく。
誰が何と言おうと、人類はこれを許してはならない。
本稿の概要は以下の音声プレイヤーの「▶」でお楽しみください。
前書き
目次
**********************
「正」の再考:漢字の起源から現代の正義・不正義を問うブログ再構築戦略
第I章 はじめに:ブログ「漢字考古学の道」の「正」再考の意義
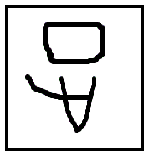 |
| 漢字「正」の甲骨文字 |
特にトランプ政権の誕生以来、前稿で論じた「正義」なんていうものは、征服者の屁理屈から生まれたものだ」という規定が、悲しいかなそのまま当てはまり、特にトランプ第2次政権以降は、『「正」を標榜しながら、「正」を貶(おとし)める:辱める』ことが世界中で横行し、世界の政治は地に堕ちたといっても過言ではない有様です。
既存の記事は、「正月」や「正義」といった言葉に用いられる「正」という漢字が、その成り立ちにおいて「恐るべき不正義」を内包している可能性を指摘していました 。
しかし、その後の事態の進展?は哲学でいう「量から質への転換を果たした」状況です。
状況がこのように大きく変貌している中で、前項の執筆者として前項のまま放置することは、執筆者の責任を放棄したということになります。そこで意を決して前稿「漢字 正の成り立ちの意味するもの」を全面的に改定することとしました。
したがって、本レポートの目的は、漢字「正」の意味を問い直すと同時に、漢字が意味が、現実の社会の中でどう変化するかを歴史的、哲学的視点から深く掘り下げて分析することにあります。
本レポートは、「正」の漢字の成り立ちに関する学術的議論から出発し、「正義」概念の東西哲学における比較検討、現代社会における「正義」と「不正義」の具体的な事例分析へと展開します。
最終的に、これらの深い考察に基づき、「正義」という思いや思想が観念的に純粋に決まるものではなく、社会的、階級的な立場の中で、決まっていくものだということを明らかにすることを目指します。このことによって、「正義」はお題目のように唱えることによっては決して獲得できるものではないことも共通の認識になることを期待します。
II. 漢字「正」の深層:多角的な字源論と歴史的変遷
漢字「正」の字源を巡る議論は多岐にわたり、その原初的な意味から現代的な「正しい」という概念への変遷は、言語と社会の複雑な相互作用の結果であることを示唆しています。「正」の甲骨文・金文における原初的意味の探求
「正」の甲骨文や金文に見られる初期の字形は、その原初的な意味を解き明かす鍵となります。主要な学説は、大きく二つの系統に分けられます。
- 「一/囗」+「止」説(征服・進撃の意)
- 「止」+「丁」説(音符と目標の意)
これに対し、Wiktionary や一部の学術論文 では、「正」は「止」と音符「丁」からなる形声文字であるという説が提示されています。この説によれば、「丁」は「討伐する」を意味する「征」の音符であり、漢字の上部に位置する「一」は、もともと円形や長方形であった「丁」字が時代とともに簡略化された形であるとされます 。この見方は、『説文解字』が「一」+「止」と分析した点について、初期の字形を考慮していない誤った分析であると指摘しています 。
「丁」が「釘の頭」の象形であり、また古代において公用に徴発された人民を意味する「よほろ」とも関連付けられることがある点は、この漢字の多面的な背景を示唆します
 |
| 漢字「正」甲骨、金文、小篆、楷書 |
この二つの字源論が学術的に対立している事実は、単なる事実の相違以上の意味を持ちます。初期の漢字分析(例えば『説文解字』)は、後代のより抽象化された字形(小篆)に基づいて行われることが多く、それが元の意味の誤解につながる場合がありました。
甲骨文や金文といったより古い文字資料の研究が進んだ現代の古文字学では、より正確な字形と意味の復元が可能になっています 。しかし、たとえ厳密な言語学的な観点から「征服」の起源が唯一の、あるいは主要な語源ではないとしても、その解釈が「正」という漢字、特に「征」や「政」との関連において文化的に与えてきた影響は否定できません。ブログにおいては、この学術的な議論の存在を提示し、なぜこのような議論があるのか(初期字形の重要性)を説明することで、コンテンツの学術的な深みと批判的思考の側面を強化できます。
主要な字書・学説の比較と考察
「正」の字源に関する学術的な多様性は、主要な字書や学者の解釈を比較することでより明確になります。
- 『漢字源』の解釈: 『漢字源』は、「正」を「一(一直線)+止(あし)」の会意文字とし、足が目標の線に向かってまっすぐに進む情景を示す「征」の原字であると簡潔に説明しています 。しかし、この字書は古文字字形への注意が不足していると批判されることがあります。特に、上部の「一」が初期には「丁」字と同様に円形や長方形であったという点を考慮していないと指摘されています 。
- 『字統』(白川静)の解釈: 白川静氏の『字統』では、「正」は「一」と「止」に従い、「一」が城郭に囲まれた邑を、「止」がそれに向かって進撃する意味で、邑を征服することを意味し、「征」の初文であると説明されています 。白川文字学は、甲骨文や金文に深く精通し、漢字を神の依代づくりや、文字の担い手の動作に連動させて解釈するという独自のアプローチを特徴としています 。彼の学説は、「正なるもの」と「負なるもの」を連続的な作用として捉える視点も内包しています 。
- 『漢語大字典』の解釈: 『漢語大字典』は、甲骨文や金文において「正」が「止」と「丁」(音符)から成り立っていると説明しています。「丁」は行程の目標や城邑を示し、人が足で目標に向かって進む象形であり、「征」の初文であるとされます 。本義は「遠行」ですが、後に征伐の意味に偏重し、「正」が糾正や偏正の意味に多用されたため、区別のために「彳」(ぎょうにんべん)を加えて「征」という字が分化されたと解説されています 。また、「正月」や「官長」といった意味も持つことが記されています 。
- 山田勝美『漢字の語源』の解釈:
山田勝美氏の『漢字の語源』では、「正」の上部「―」の古い形(□のような形)は城壁ではなく、膝頭の象形であるという全く異なる説が提示されています。膝から下が曲がらないことから「直」の意味に通じ、そこから「ただしい」の意味になったと解釈されています 。この説は、「正」が戦争を意味するという説とは対照的な、より普遍的な「まっすぐさ」を起源とする見方です。
このように、「正」という漢字には、複数の、時には矛盾する字源論が存在します。これは、漢字の歴史的変化の複雑さと、意味が時代とともに多層的に形成されてきたことを示しています。ブログにおいては、この学術的な多様性を提示することで、漢字の語源の「正しさ」が必ずしも単一ではないことを読者に伝え、現代の「正義」概念の流動性や多様性へと議論を繋げることができます。特に、「征服」を起源とする説は、現代の「不正義」を批判的に考察する上で強力なレンズを提供しますが、「まっすぐさ」を起源とする説は、より普遍的で肯定的な「正しさ」の基盤を示し、これらの解釈の相互作用が議論を豊かにします。
「正」から派生した「征」「政」との語源的・意味的関連性
「正」という漢字の語源的探求は、その派生字である「征」や「政」との密接な関連性から、権力の正当化という歴史的側面を浮かび上がらせます。多くの学説が指摘するように、「正」はもともと「征服」の「征」の原字であり、その意味から「征」という漢字が生まれました 。これは、古代において、ある地域に進攻し、支配下に置く行為が「正」であると認識されていた可能性を示唆しています。
 |
| 漢字「正」の4款 甲骨文字の右の図はこん棒(たて棒)を持つ手を表すとされる |
「正」の意味拡張と「正しい」概念の形成過程
「正」という漢字の意味は、その原初的な「征服」や「進撃」といった意味合いから、より抽象的で普遍的な「正しい」という概念へと拡張されてきました。一部の解釈では、「正」の本来の意味は「到達目標」や「直線前進」であり、そこから「偏り」「斜め」「湾曲」とは対照的に「中正」「正直」といった意味に拡張されたとされています 。
現代日本語における「正しい」という言葉は、その意味が多岐にわたります。「形や向きがまっすぐである」という物理的な意味から、「道理にかなっている」「事実に合っている」という論理的な意味、「道徳・法律・作法などにかなっている」という規範的な意味まで、多様な文脈で用いられます 。
「正月」という言葉も、「正」の意味拡張の一例です。これは中国の暦法において一年の基準となる月を指し、「改正」という言葉は、王朝が変わった際に正月の基準を改めて暦を新しく定めることを意味します 。これらの用例は、「正」が「基準となるもの」や「規範」という意味を持つようになったことを示唆しています 。
漢字「正」が、潜在的に暴力的であったかもしれない起源から、「まっすぐさ」「正確さ」「基準」といった概念へと意味を広げてきたことは、人類の価値観の進化が言語にどのように刻み込まれてきたかを示す興味深い例です。この二重性は極めて重要です。ブログは、この一文字が、古代の「正しさ」の強制的な側面と、後に普遍的に受け入れられるようになった「正確さ」や「公正さ」といった理想の両方をどのように体現しているかを探求できます。この歴史的な意味の重層性は、現代社会において「正義」が主張されながらも、その行動がより倫理的な「正しさ」の定義と矛盾する状況を批判的に考察するための強力な基盤を提供します。
III. 「正義」概念の歴史的・哲学的考察
「正義」という概念は、時代や文化、哲学的な伝統によってその解釈が大きく異なり、常に権力との複雑な関係性の中で形成されてきました。したがって、そのとらえ方は、非常に大雑把ではあるけども、西洋哲学においては外部の法律や社会構造に焦点を当てるのに対し、東洋では特に仏教や道教は、「正しさ」や「正義」に対してより内省的で全体的な見方を提供しているようです。
西洋における「正義」の概念
西洋哲学における「正義」の探求は、古代ギリシャにその源流を持ちます。古代ギリシャの都市国家(ポリス)において、「正義」は、共同体の秩序維持と調和、そして共同体にとっての「善」、すなわち「公共善」を目指すものとされました 。- プラトンは、『国家』において「正義」を人間の魂の調和の問題として深く考察しました。
- 一方、アリストテレスは、政治的な動物である人間にとっての共同体の「善」とは何かを政治的に検討しました 。アリストテレスは、「正義とは人をして正義ならしめる状態」であると述べ、治世が民衆に支持されるのは、「万人の功益がある」と同時に「支配者の功益をもかなえる」政治や税制であると論じました 。しかし、彼の「正義」の視点には、為政者側の視点が含まれており、必ずしも民衆の視点のみに基づいているわけではないと指摘されることもあります 。
- 中世キリスト教の時代に入ると、トマス・アクィナスが「共通善」を社会の最高規範と位置づけ、平和を最も重要なものとしました 。
西洋思想における「正義」のこの歴史的軌跡は、「共通善」の追求として枠付けられた場合でさえも、「正義」がしばしば支配権力の視点から定義され、強制されてきたことを示しています。アリストテレスが支配者の利益と民衆の利益の双方を強調した点は 、「正義」が既存の権力構造を維持するための道具として機能しうるという考え方を補強します。これは、漢字「正」の「征服」という起源と響き合い、ブログ運営者が指摘する「正義を標榜しながら不正義を働く行為」という現代の問題に対して、西洋哲学においても同様の権力と「正義」の間の緊張関係が存在することを示唆します。
日本の現行憲法にも学者の間には「帝王条項」と呼ばれる条項があります。それは、「公共の福祉」という文言です。まさに「共通善」と定義づけられた概念そのままです。
こうして考えると「正」が「民」の全体にとっての正か、「個々の民」にとっての「正」かと捉えることに趣を異にします。とすれば、「正」も全体に捉えることと、「個」として捉えるということに帰結します。ここで初めて、「正」を民主主義の問題として捉える大切さを思い知ることになると思います。
東洋における「正義」の概念
 |
| 「正」はしばしば「民」を攻撃する |
東洋思想の多様な側面は、「正」という漢字の「征服」という起源や、権力中心の「正義」観に対する重要な対抗軸を提供します。
儒教の「義」と「仁義礼」の思想
儒教における「正義」観は、「仁、義、礼」という核となる概念に深く根ざしています 。このうち「義」は、「正義と道義を重んじる心」であり、「人として守るべき道徳、道理、正しい行い」を意味します 。
- 孔子は「義」を個人の修養の側面から論じ、君子と義の関係、そして義と利の関係を強調しました 。彼は「不義にして富み且つ貴きは、我に於いて浮雲の如し」と述べ、利益を追求する過程においても「義」によって自らを律することの重要性を示しました 。
- 孟子は「仁、人の安宅なり。義、人の正路なり」と述べ、「義」を人が歩むべき「正しい道(正路)」と位置づけ、その根源を人の内なる「羞悪(しゅうお)の心」(不正を恥じ憎む心)に求めました 。彼は「先義後利」(義を先にして利を後にする)という考え方を提唱し、目先の利益にとらわれず、人としての正しい行いを優先すべきだと説きました 。
- 荀子は「正義」という言葉を初めて使用したことで知られています 。彼は「義」を社会制度の基盤として位置づけ、「正利而為謂之事,正義而為謂之行」(正当な利益のための行動を事といい、正義を貫くための行動を行という)と述べ、正義を行動の前提となる道徳的基準としました 。荀子は、仁、義、礼の三者が社会の秩序を構築する上で不可欠であると考えました 。
仏教・道教における「正しさ」の捉え方と倫理観
- 仏教においては、八正道(正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定)に従うことが重要であり、苦しみを減らすことが善とされます 。仏教は人間の欲望や執着が苦しみを生むと考え、それを断ち切り、心を静かに保つことが解脱への道であると教えます 。また、輪廻や因果応報の概念を通じて、個々の行動が未来に影響を与えるという倫理的な教えも重視されます 。
- 道教では、自然との調和を重視し、「無為自然」の生き方が倫理的とされます 。道教は、自然の流れに逆らわず、自然に任せることで倫理的な行動が自然に生まれると考えます 。また、「道」の理念は現世の権力に勝る理念であるとされます 。
西洋哲学がしばしば外部の法律や社会構造に焦点を当てるのに対し、東洋思想、特に仏教や道教は、「正しさ」や「正義」に対してより内省的で全体的な見方を提供します。儒教も社会秩序と統治を扱いますが、「仁」や「義」を人間本来の資質として強調する点は、外部の権威だけでなく、人間性そのものに道徳的基盤を求める姿勢を示します 。仏教の苦からの解放と倫理的行動への焦点は、「正しさ」の所在を個人の精神的実践へと移します 。道教の「無為自然」は、真の「正しさ」が人為的な規則を超え、宇宙の自然な流れと調和することにあると示唆します 。これらの東洋思想の多様な側面は、「正」という漢字の「征服」という起源や、権力中心の「正義」観に対する重要な対抗軸を提供します。ブログは、このような広範で繊細な「正しさ」の理解を探求することで、現代の「不正義」を批判するためのより豊かな枠組みを提示できます。
権力と「正義」の関係性:征服者の論理から為政者の「正当性」へ
「正」という漢字の字源が「征服」を指す可能性があるという解釈は、歴史を通じて「正義」がどのように権力と結びついてきたかを示す重要な手がかりとなります 。歴史を振り返れば、「勝てば官軍」という言葉が示すように、戦争に勝利した側が自らを「正義」と称し、敗者を「不正義」と位置づける傾向がしばしば見られました 。第二次世界大戦後の東京裁判やニュルンベルク裁判は、この現象の典型的な例です 。
西洋哲学のアリストテレスの「正義」概念においても、その視点には為政者側の利益が含まれることが指摘されています 。これは、「正義」が単なる普遍的な倫理原則ではなく、既存の権力構造を維持し、行動を正当化するための手段として機能しうることを示唆します。
歴史的な言語の起源から哲学的な議論に至るまで、一貫して見られるのは「正義」と権力の間の強く、時に問題のある関連性です。「正」の「征服」を意味する起源は、単なる言語学的な好奇心ではなく、歴史的な真実を深く示唆しています。すなわち、
「正しいこと」や「正義」は、しばしば自らの意思を強制する力を持つ者によって決定されてきたという事実です。このことは、「正義」がしばしば相対的な概念であり、支配的な物語や権力構造によって定義されることを示唆します。この歴史的パターンは、ブログ運営者が懸念する「正義を標榜しながら不正義を働く行為」という現代の偽善を直接的に裏付けるものです。それは、「正義」が自己奉仕的な目的のための単なる道具と化す内在的な危険性を浮き彫りにします。ブログは、この歴史的文脈を用いて、現代において権力を持つ立場から発せられる「正義」の主張を批判的に検証するよう読者に促すことができます。
IV. 現代社会における「正義」と「不正義」の実態
現代社会において「正義を標榜しながら不正義を働く行為」が横行しているというブログ運営者の問題意識は、個人の倫理観の問題に留まらず、より広範な社会的・構造的な要因に根ざしていることが、様々な事例から明らかになります。「正義を標榜しながら不正義を働く行為」の構造的分析
現代社会に蔓延する「構造的不正義」は、特定の個人の悪意ある行為によって引き起こされるだけでなく、多数の人が関わる社会のプロセスやシステムを通じて生じることが特徴です 。これは、企業や組織における不正行為の背景にも共通して見られます。
例えば、企業における不祥事の多くは、過剰な営業ノルマ、社員間での罰金制度、売上至上主義といった組織文化、管理職による不適切な指示、あるいはコンプライアンス教育の不十分さなど、構造的な問題に起因することが指摘されています 。このような環境下では、個々の従業員が「正しい」と信じる行動よりも、組織の目標達成や自己保身が優先され、結果として「不正義」な行為が「正当化」されてしまう現象が発生します。
この構造的分析は、不正義を単なる個人の道徳的欠陥として捉えるのではなく、それが組織的・制度的な枠組みの中でどのように発生し、維持されているかを理解するための洗練された枠組みをブログに提供します。これは、ブログ運営者の当初の観察が、個人の「悪役」を非難するだけでなく、偽善を可能にする根底にあるメカニズムに疑問を投げかける、より深い批判へと発展しうることを示唆します。現代の不正義に対処するには、道徳的な訴えだけでなく、システム全体の改革と組織的価値観の再評価が必要であるという結論を導き出します。
具体的な事例分析
「正義を標榜しながら不正義を働く行為」は、企業、政治、国際関係といった様々な領域で具体的に観察されます。
企業倫理・不祥事
企業活動における不正は、利益追求が倫理的「正義」を歪める典型例です。
例えば、中古車販売大手における保険金不正請求のための故意の車両損壊や、不要な部品交換、その背景にあった過剰な営業ノルマや社員間の罰金制度は、企業が掲げる「顧客への正当なサービス」という建前と、実態の「不正義」との乖離を示しています 。
また、旅行会社による全国旅行支援キャンペーンに関する人件費の架空計上や不正請求は、公的制度の「正当な」利用を装いながら、実際には税金の不正受給を行っていた事例です 。
アルバイト店員による悪ふざけ動画のSNS炎上は、企業のブランドイメージや顧客からの信頼を大きく損ない、衛生管理やモラルに対する不信感を招きました 。
その他、業務用PC端末からの情報流出 、大手広告代理店における新人社員の過労死(安全配慮義務違反、マネジメント・組織体質の問題) 、上司によるハラスメント 、SNSイラストの無断使用・盗作 、雇用調整助成金の不正受給、不正勧誘、食品偽装、景品表示法違反、インサイダー取引、顧客情報の不正利用、役員によるセクハラなど 、枚挙にいとまがありません。
これらの事例は、利益や効率性の追求が、いかに企業構造の中で「正義」を歪めうるかを示しています。企業は、対外的には「正しさ」や責任を標榜しながら、実際には倫理的・法的な「正義」に反する行為に従事します。これは、「征服者の屁理屈」が現代の企業における「屁理屈」へと形を変えて現れているとも解釈できます。結果として、経済的損失だけでなく、社会的な信頼の喪失という深刻な代償を支払うことになります 。
政治スキャンダル・腐敗
政治における「正義」の道具化は、権力維持の論理と密接に結びついています。
例えば、グアテマラの政権与党が「政党というより暴力団に近い。その役割は国を略奪することにある」と評される事例は 、為政者が「国民のため」という「正義」を掲げながら、実際には私腹を肥やす「不正義」を働く典型です。
中国共産党内部の権力闘争の歴史、例えば林彪や華国鋒の失脚、鄧小平による後継者制度の構想などは 、政治における「正しさ」が、権力闘争の勝者によって流動的に再定義されることを示唆しています。
日本のリクルート事件もまた、未公開株の贈賄を通じて政財界が癒着し、当時の内閣が退陣に追い込まれた事例であり 、権力が「正義」を装いながら不正を働く構造が社会の根幹を揺るがすことを示しました。
ジャニーズ性加害問題や日大アメフト部の大麻汚染など、かつては「見過ごされてきた」スキャンダルが近年表面化している現象は 、社会の規範意識の変化や、隠蔽されてきた不正義が明るみに出るようになったことを示唆します。
これらの事例は、政治における「正義」が、公共の利益のためではなく、自己保身や不正な利益のために利用される道具と化す危険性を強調します。古代の征服者が自らの行動を「正」としたように、現代の政治家もまた、自己奉仕的な目的のために「正義」のレトリックを用いることがあります。
国際関係・紛争における「正義」の対立
国際関係においては、「正義」の概念はさらに多義的であり、それが紛争の根源となることが少なくありません。
歴史を振り返れば、戦争において勝者が自らを「正義」と名乗り、敗者を「不正義」と位置づける傾向がしばしば見られました 。第二次世界大戦後の東京裁判はその典型です 。
国際人道法(ハーグ陸戦条約、ジュネーブ諸条約)は、戦争における「正義」を問う試みとして、捕虜や傷病者の扱い、使用してはならない戦術などを定めていますが 、その違反は後を絶ちません。
現代の国際紛争、例えばシリア内戦における複数の勢力間の争い、クルド対トルコ紛争、リビア内戦、ウクライナ侵攻などは 、それぞれが自らの行動を「正義」と主張し、複雑な利害が対立する中で解決が困難な状況を生み出しています。
領土問題(北方領土、ハラーイブ・トライアングルなど)や国境紛争における国際司法裁判所の判決は、「正義」の追求と国際法の適用による解決の試みですが 、すべての紛争が法的に解決されるわけではありません。東ティモールでは、「正義追求」と「和解」のどちらを優先すべきかという国民の意見対立が見られました 。
国際関係における「正義」は、普遍的な合意が困難な多面的な概念であり、各国家や勢力が自国の利益や歴史的経緯に基づいて「正義」を主張することで、紛争が長期化する根源となります。これは、国家が自国の行動を正当化するために、国家の利益、安全保障、あるいは歴史的主張の旗印の下に侵略や抑圧を正当化する「正義を標榜しながら不正義を働く行為」が顕著に現れる場です。国際人道法の存在は、紛争における「正しさ」の普遍的基準を確立しようとする試みですが、その頻繁な違反は、主張される「正義」と実際の行動との間に存在する根強い乖離を浮き彫りにします。
構造的不正義の概念と現代的課題への示唆
「構造的不正義」という概念は、現代社会における「不正義」を理解する上で極めて重要です。これは、一人の個人の行為によって引き起こされるのではなく、多数の人が関わる社会のプロセスやシステム、慣習の中に内在する偏見や不平等によって生じるものです 。性差別、移民差別、グローバルな貧困、植民地支配の遺産、気候変動などがその具体的な例として挙げられます 。
例えば、労働問題における不平等や格差の是正が世界中で依然として困難であることは 、構造的不正義が社会の深部に根ざしていることを示します。また、植民地支配への批判と反省、人種的不正義への糾弾(BLM運動など)は、歴史的に形成された構造的不正義を認識し、その是正を求める動きです 。
この概念は、ブログの現代的な関連性を高める上で不可欠です。それは、「不正義」を単なる個人の責任としてではなく、社会システムに内在する偏見や不公平の結果として捉える視点を提供します。不正義が構造的である場合、個々人を罰するだけでは不十分であり、真の「正義」を実現するためには、その根底にある社会的、経済的、政治的構造の再検討と変革が必要となります。この構造的分析は、漢字「正」の歴史的起源と権力との結びつきが、いかに現代の社会構造の中で不正義を永続させうるかを明らかにし、「漢字考古学」を現代社会分析の強力なツールへと昇華させます。
第V章 結論:漢字「正」から現代の「正義」を問い直す
本レポートは、ブログ「漢字考古学の道」の既存記事「漢字 正の成り立ちの意味するもの」の再構築を支援するため、多角的な視点から「正」という漢字と「正義」概念を深く掘り下げました。主要な発見として、まず漢字「正」の字源が持つ多義性、特に「征服」と「まっすぐ」という対照的な意味の変遷を詳細に分析しました。これは、漢字の初期の字形を根拠とする学術的議論が存在し、その解釈が「正」の概念形成に与える影響が大きいことを示しています。
次に、「正義」概念が西洋・東洋の哲学においてどのように発展し、また権力との関係性の中でいかに定義されてきたかを考察しました。特に、征服者や為政者の論理が「正義」の定義に影響を与えてきた歴史的傾向は、現代社会の偽善を理解する上で重要な示唆を与えます。
そして、現代社会における「正義を標榜しながら不正義を働く行為」が、個人の問題だけでなく、企業、政治、国際関係における「構造的不正義」に根ざしていることを具体的な事例を通じて分析しました。これらの知見は、現代の不正義がシステムや文化に深く組み込まれていることを示しています。
これらの深い考察を踏まえ、「漢字考古学の道」は、単なる漢字の解説ブログに留まらず、古代の文字に現代社会の深層を読み解く「考古学的」な視点を提供することで、読者に新たな気づきと批判的思考を促すユニークなプラットフォームとしての役割を果たすことができますると信じています。このブログは、漢字の起源という学術的関心を出発点としながらも、それを現代の倫理的・社会的問題へと接続することで、読者が日々のニュースや社会現象をより深く、多角的に理解するための手助けとなるでしょう。
今後も、「正」以外の漢字や概念についても同様のアプローチで深掘りし、ブログの専門性と社会貢献性を高めていくことが期待されます。「漢字考古学の道」が、表面的な情報に惑わされず、物事の本質を深く探求することの重要性を訴え、読者一人ひとりが自ら「正しさ」とは何かを問い続けるきっかけとなることを強く期待します。
| 「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。
|
4 件のコメント:
「正」の原義の解釈がこれほどに異なるとは、また、 「征」という漢字の由来ともいうのは、全く、無知で知らないことでした。 漢字一つから、歴史的、社会的、世界的視野、また、現代の諸問題での考察は、非常に 複眼的で示唆に満ちていると思えます。世界中の現代人がこのような広い視野を持って、生きてほしいものです。
世界中の方々夫々に広い視野を持っておられるのではないかと思います。去年もコロナのパンデミックの中で多くの意見が叫ばれました。中でも特に目立ったのは色々の「陰謀説」でした。しかし、私は逆説的かもしれませんが、多くの人が「これは陰謀だ」というなら、それは最早陰謀とは言えないように思うのです。逆に「これは陰謀というほうが陰謀ではないかと思ったりもするのです。投稿された方も言うように、「広い視野を持って」何が正しいのか、何が正義かを今一度立ち止まって考える寛大さ、落ち着き、慎重さが望まれるのではないでしょうか?特にAIの発展によって誰でもが多くの情報を簡単にできるようになった現代、「本当に正しいのか」という見極めこそが世界中の現代人に求められているように感じます。
漢字の字源を調べていたら行きつきました。文字の持つ古今東西の意味。成り立ち。そこを解釈すると見えてくるものが文化。とても良いブログです。今後も引き続き鋭い分析解釈期待しています。
このページは更新し、新しいページを立ち上げましたので引き続きご購読いただければ幸いです。
コメントを投稿
ブログ「漢字考古学の道」をお尋ねいただきありがとうございます。